

書名 : ピーチとチョコレート
著者 : 福木 はる/著
出版社 : 講談社
ありのままの自分でいることは、案外と難しいものです。
中学生の萌々は、太っていることがコンプレックス。自信のなさから、笑われる前に笑わせてやれと、おどけたキャラを演じています。けれど言葉と気持ちがバラバラで、本音を言えない辛さも感じていました。
そんな萌々が「人生、変わるよ?」と気になる言葉で誘われて、習い始めたのはヒップホップのラップ教室。
そこには学校で孤立しているクラスメイトの莉愛もいて、二人は次第に親しくなります。ミックスの莉愛は、チョコレート色の自分の肌が好きなのに、いつも隠すようにフードを目深に被っていました。
二人がそれぞれのコンプレックスを乗り越えて、「ルッキズム(外見至上主義)の墓たてろ!」とパワフルに歌う、文化祭のラップバトルは圧巻です。
ずっと反対側にあると思っていたポジティブとネガティブ。最後に萌々がたどり着いた答えとは?
勇気をくれて、心に響く物語です。
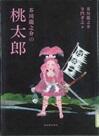
書名 : 芥川龍之介の桃太郎
著者 : 芥川 龍之介/文 寺門 孝之/画
出版社 : 河出書房新社
みなさんは桃太郎が鬼退治に行った理由を思い出せますか。悪い鬼がいたから、財宝を貯めこんでいたから……実は、本によってその理由はさまざま。ほかにも小さな違いはあるけれど、桃太郎がお供を連れて鬼を退治するという大筋は同じ。こうした話のわずかな空白を利用して、芥川独自の桃太郎像が生まれています。
さて、この本で桃太郎が鬼退治に行く理由は「仕事に出るのがいや」だったから。お爺さんもお婆さんも、なまける桃太郎を追い出したくて出陣の支度を手伝います。
よこしまな考えをもった桃太郎とは逆に、平和を愛する鬼たち。討伐後、桃太郎は平穏な日々を送ったでしょうか。鬼たちは変わらず平和を愛したでしょうか。
決して「めでたしめでたし」では終わらない『芥川龍之介の桃太郎』。本当の鬼とは何か考えるとき、私たち人間の在り方についても見つめなおさなければなりません。
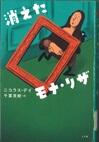
書名 : 消えたモナ・リザ
著者 : ニコラス・デイ/作 千葉 茂樹/訳
出版社 : 小学館
1911年8月21日、フランスのルーブル美術館から「モナ・リザ」が盗まれた!犯人はその日、美術館に忍び込んだのではない。前日、そこに残ったのだ。
大胆不敵な犯罪、異常なコレクターが犯人なのか?それとも「モナ・リザ」を熱烈に愛する者の仕業なのか?いろいろな憶測が飛び交い、世界中から注目が集まる中、犯人は捕まえられなかった。
そして約2年後、事件は急展開を迎える。「モナ・リザ」はルーブル美術館に戻ってくることになった。それもとてもいい状態で…。
一部の人にしか知られていなかった「モナ・リザ」は、盗難そして返還されたことによって、世界的に有名な作品となった。この小説はその経緯と背景、レオナルド・ダ・ヴィンチの人生を織り交ぜながら描いたノンフィクションである。
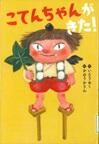
書名 : こてんちゃんがきた!
著者 : いとう みく/作 かのう かりん/絵
出版社 : 理論社
転校生のこてんちゃんは、着物姿のおかっぱ頭に烏帽子をかぶり、手には葉うちわを持って、上履きではなく一本歯下駄を履いています。さらに、その背中にはなんと羽が生えていたので、クラスのみんなは変なのと思います。
しかし、こてんちゃんはマイペース。先生の話はちっともきかず、授業中に「おなかがすいた」と言ってしまいます。その一方で、走りにくい下駄を履いているのに、かけっこで1番になったり、楽しくなると踊ったり、きれいなお母さんが授業参観に来てくれて嬉しそうだったりする様子も。そんな素直で天真爛漫なこてんちゃんと過ごすうちに、誰もこてんちゃんを変だと思わなくなりました。
かのうかりんさんが描くこてんちゃんが魅力的で愛らしく、人と違っていてもいいんだよ、と安心させてくれる一冊です。

書名 : やってみた!研究イグノーベル賞
著者 : 五十嵐 杏南/著
出版社 : 東京書店
みなさんは、イグノーベル賞という賞を知っていますか?ノーベル賞ではありません、“イグ”ノーベル賞です。この賞は「人を笑わせ、その後、考えさせる」研究や実験に贈られる賞です。
例えば、ワニが鳴き声を出す仕組みを調べるためにヘリウムを吸わせた実験。ワニの声が変わったことで、ワニは人と同じ仕組みで声を出していることがわかりました。
ほかにも、バッタの脳の動きをみるために映画を見せる実験、コーヒーをこぼさずに歩く方法の研究など、受賞した実験や研究は一見おもしろおかしいものばかりです。
しかし、ただ笑えるだけではなく、様々な分野で実際に役立っている研究もたくさんあるのが、イグノーベル賞のすごいところです。ちなみに、日本人は2024年まで18年連続で受賞しているそうです。
紹介されている研究者たちのようにユニークな視点で物事を見てみると、思いがけない大発見で世界を変えることができるかもしれませんね。
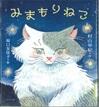
書名 : みまもりねこ
著者 : 村山 早紀/作 坂口 友佳子/絵
出版社 : ポプラ社
この物語は、一匹のおばあさん猫と女の子の絆のお話です。
命の終わりが近づいてきたおばあさん猫の唯一の気がかりは、いつも寂しそうに泣いている女の子のこと。自分の命が終わる直前に、あの子のそばに居たいと星に願いました。願いが叶った猫は、死後、透明な見えない猫になります。
女の子は猫の死を知って悲しみますが、その夜、女の子の夢の中で猫が語りかけます。『ずっとそばにいますからね。みえないけれど、いっしょなの。だから、なかないで』と。
それから女の子は泣かなくなりました。いつも傍には見えない猫がいると信じていたからです。そして、女の子は成長し、大人になった彼女のもとに現れたのは…。
いつも寂しそうにしている女の子に母のように寄り添う猫。柔らかなタッチで描かれる風景の中で、ページいっぱいに描かれる夜空の星はずっと眺めていたいほど印象的です。
種族と時を超えた、大きな愛に心が温かくなる一冊です。

書名 : こうして、ともにいきている
著者 : 多屋 光孫/作
出版社 : 汐文社
だれかと同じ場所で同じものがほしくなったとき、あなたならどうしますか。早い者勝ち?相手にゆずって自分はあきらめる?
この本に出てくる生き物たちが導き出した答えは、わたしたち人間にとって、だいじなことを気づかせてくれます。
たとえば、同じ川にすみ、同じえさを食べるヤマメとイワナの場合、ヤマメは水の温かいところで、イワナは冷たいところでえさをとります。争わず、ともに生きていくためのじょうずな方法がそこにはあるのです。
ほかにも、「なるほど」と感心する方法でともに生きている自然界の生き物たちが、生命感あふれるダイナミックな色彩とタッチで描かれています。
そして、最後に登場するのは…。
果たして、「ともに生きるということの大切さ」を忘れた生き物の未来はどうなるのでしょう。また、最後のページで投げかけられた問いに、みなさんはどう答えますか。

書名 : 雪娘のアリアナ
著者 : ソフィー・アンダーソン/作 メリッサ・カストリヨン/絵 長友 恵子/訳
出版社 : 小学館
身体が弱りひとりで農場を営めなくなった祖父と暮らすため、両親と北の山村に越してきたターシャ。ターシャは、以前住んでいた海辺の町で起きたある事件のせいで人と関わることをひどく恐れるようになっていて、村に来て3か月経った今も友だちがいません。大好きな祖父と両親との農場の生活は楽しいけれど、ターシャはいつも孤独を抱えていました。
初雪の日、ターシャは雪で少女の像をつくり「友だちになって」と強く願います。すると雪像に魂が宿り、ターシャは毎晩農場を抜け出し雪娘アリアナと楽しい時間を過ごすように。「アリアナとずっと一緒にいたい」とターシャは願いますが・・・。
ロシアの民話「雪娘」をモチーフにした物語です。春になれば雪娘は消えてしまいます。けれど、アリアナと一緒にい続ける限り厳しい冬が続き、祖父はどんどん弱っていきます。ターシャはどうするのでしょうか。
ターシャと周囲の人々が互いを思いやる優しさにあふれたお話です。

書名 : たまごのはなし
著者 : しおたに まみこ/作
出版社 : ブロンズ新社
表紙に鎮座するのは、手を組み絶妙な表情でこちらを見つめるたまご。この物語の主人公です。
長いことキッチンでじっと動かずに転がっていたたまごは、ある日突然立ち上がってみることにしました。頭を一口かじってみたことがきっかけで仲間になったマシュマロと、たくさんの初めてを経験します。「当たり前」を押し付けてくる植木鉢の口にテープを貼ってみたり、気ままなたまごたちを羨む、「大事な仕事」がある時計の電池を抜いてみたり。そうすれば仕事をせず休めるから、というたまごの言い分が辛口で爽快です。
長い間、転がっていて動く素晴らしさに気付いたばかりのたまごに先入観なんてものはありません。本当に困ったたまごだとマシュマロが言うように発言や行動には少し毒があるけれど、その哲学にはハッとさせられる大切なことが詰まっています。
ほぼ鉛筆で描かれた薄暗い絵の中で繰り広げられるたまごたちの不思議な日常を、あなたも覗いてみませんか?
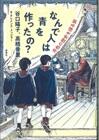
書名 : なんで人は青を作ったの?
著者 : 谷口 陽子/著、髙橋 香里/著、クレメンス・メッツラー/画
出版社 : 新泉社
「青色」は好きですか?
目にも涼しげな青は、晴れ渡った空や浮世絵に波とともに描かれた海のイメージがありますが、かつて絵の具の材料であるウルトラマリンブルーという「青色」1グラムは、「金」1グラムと同じ価値だったのだとか。
この本では、中学1年生の蒼太郎と律が、「青」という色が貴重だった謎について、人類が青色を手に入れた再現実験に挑戦しながら解き明かしていきます。2人のサポート役は骨董店の店主で元大学教授のちょっと変わった化学者、森井老人。ヴェルディグリ、スマルト、エジプシャンブルー、プルシアンブルーなど「青」にもいろいろありますが、それぞれの「ブルー」の原料や素材、作られた方法はどのようなものだったのでしょう。2人の実験は、壮大なブルーの歴史を巡る旅となり、やがてこの経験は少年たちを少しだけ成長させたようです。
ぜひ、みなさんも「青」を探す旅に出ませんか。