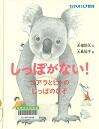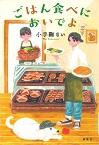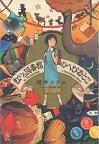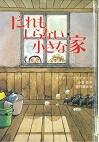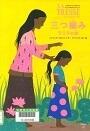小中学生へおすすめ!
児童書おすすめ(11月28日)
書名 :『惑星のきほん』
著者 :室井 恭子・水谷 有/著
出版社 :誠文堂新光社
--------------------------------------------------------------------
私たちの暮らす地球は太陽系の『惑星』という種類の星です。太陽の周りを回る惑星は他にも火星や金星などがあります。 惑星にはそれぞれ特徴があり、この本ではそんな惑星の特徴を写真やイラストを交えて、やさしく解説しています。たとえば、太陽に一番近い水星は1日がとても長く、地球での176日が水星での1日になります。木星に見える模様のようなものはとても大きな嵐です。大きさは地球がすっぽり入るくらいで、300年以上も続いています。 このように地球ではありえない環境やびっくりするような自然現象が、他の惑星にもまだまだたくさんあります。また、なぜ地球にだけ生命が存在しているのか、火星人はいるのかなどの疑問にも答えてくれます。宇宙には数えきれないほどたくさんの星がありますが、まずはこの本で身近な惑星について知ってみませんか?きっと宇宙や星についてもっと知りたくなるはずです。
児童書おすすめ(11月21日)
書名 :『小学生博士の神社図鑑』
著者 :佐々木 秀斗/著
出版社 :桜の花出版
--------------------------------------------------------------------
みなさんは「古事記」を知っていますか? 古事記は、日本の神さまの話がたくさん書いてある、とても古い本です。日本の神社は、主にこの古事記に出てくる様々な神さまをお祀りしています。 そんな古事記と神社に夢中になった小学生博士・佐々木秀斗くんの自由研究が本になりました。 日本にはどんな神さまがいるのか、どんな神社があるのか、神社とお寺の違いはなんなのか…日本の神さまと神社にまつわる様々な話が、秀斗くんのシンプルな説明とたくさんのイラスト、写真で分かりやすくまとめられています。また、日本の神さまと神社を知ることで、日本の文化、歴史、昔からの考え方にふれることができます。この本では、それまで知らなかった日本の姿も知ることができますよ。分かりやすく、大人が読んでもためになる内容となっているので、親子などで一緒に読んでも楽しめるはず。大人も子どもも、読み始めたら止まらなくなってしまう一冊です。
児童書おすすめ(11月14日)
書名 :『ディズニーのそうじの神様が教えてくれたこと』
著者 :鎌田 洋/著
出版社 :SBクリエイティブ
--------------------------------------------------------------------
みなさんは、ディズニーランドに行ったことがありますか?行ったことがない人でも、一度は行ってみたいと思うのではないでしょうか。なぜ、私たちはディズニーランドに心惹かれるのでしょうか?その秘密を知っているのが、ディズニーの「そうじの神様」です。この本は、ディズニーランドを舞台にカストーディアル・キャスト(清掃員)たちによって繰り広げられる4つの物語で構成されています。そして、この4つの物語すべてに影響を与えているのが、ディズニーの世界で「そうじの神様」と呼ばれているチャック・ボヤージン氏の教えです。物語を通して、ディズニーランドの秘密がわかり、仕事で人を幸せにするヒントを教えてくれますどんな仕事でも、大変でいいことばかりではありません。しかし、やりがいを感じて楽しいと思えることもたくさんあります。働くことの本当の意味を考えさせられる一冊です。
児童書おすすめ(11月7日)
書名 :『しっぽがない! コアラとヒトのしっぽのなぞ』
著者 :犬塚 則久/文 大島 裕子/画
出版社 :福音館書店
--------------------------------------------------------------------
りくのうえ学校で、今日も授業が始まりました。「この教室の生徒には、ひとつ大きな共通点があります。それは何だと思いますか?」いぬやま先生の質問に、みんなと自分を見くらべて一生懸命考える生徒たち。先生は、みんなの共通点は「骨があること」で、骨のある動物(脊椎動物)には、「しっぽがある」「手足が4本ある」「赤い血が流れている」という3つの特徴があることを教えてくれました。ところが、コアラのふくろいくんとヒトのあだちさんには、しっぽがありません。骨のある動物なのにどうしてなのでしょうか?この本は、「世界にあふれる“ふしぎ”を子どもたちが自らが感じ、考え、理解していけるように」との思いが込められた「たくさんのふしぎ」というシリーズの1冊です。みなさんも、りくのうえ学校のみんなと一緒に、しっぽのふしぎを探してみませんか。たくさんのふしぎを知れば、世界の見え方が変わるかもしれません。
児童書おすすめ(10月31日)
書名 :『ごはん食べにおいでよ』
著者 :小手鞠 るい/作 satsuki/画
出版社 :講談社
--------------------------------------------------------------------
ベイカリーカフェ「りんごの木」。オーナー・森崎雪の中学三年生の頃の話がこの本のメインです。ある日の夕方、自宅マンションに帰ると、同じ階に住む小学生が家に入らずに廊下の床に座りこんで膝をかかえていました。声をかければ鍵をなくしたといいます。さらに悪いことに夜9時まで家族は帰ってこないと。「よかったら、これからぼくんちに、ごはん食べにおいでよ。」曜日ごとのショートストーリー仕立ての一冊は、いろいろな人間模様を料理とともに堪能できます。
実はいま全国の図書館では「りんごの棚」というのが広がりつつあります。誰もが読書を楽しめるようにバリアフリー対策をとられた本が集められたコーナー。文字が大きかったり、点字が付いていたり、わかりやすい言葉で書かれていたり。
気軽に立ち寄りたくなる場所、りんごの木とりんごの棚。なんだか縁を感じる一冊でした。
児童書おすすめ(10月24日)
書名 :『こどもモヤモヤ解決BOOK』
著者 :熱海 康太/著
出版社 :えほんの杜
--------------------------------------------------------------------
「学校に行きたくないよ」「なんで勉強しなくちゃいけないの?」「言いたいことが上手に言えない」「SNSやゲームがやめられない」など、モヤモヤする悩みを一人で抱えていませんか?親に言いたくない、誰にも相談できない、でも自分一人ではどうしたらいいかわからない。そんな時に助けてくれるのがこの本。1つの悩みに対して3つの解決策が提案されているので、自分にあった解決方法が選べます。1つだけでもいいし、3つ全部やってみてもいい。解決策をヒントに自分で考えてもいいのです。一人一人性格や環境も違うから正しい答えというのはありません。解決の糸口となるものを見つけて自分にあった方法を実践してみてください。悩んで心や身体が疲れた時には、各ページについているもふもふした動物のかわいい写真を見て癒される、という使い方もおすすめです。
みんなの悩みがスッキリ解決する手助けとなりますように!
児童書おすすめ(10月17日)
書名 :『虹いろ図書館のへびおとこ』
著者 :櫻井とりお/文
出版社 :河出書房新社
--------------------------------------------------------------------
家庭の事情で転校したほのかは小さなことからいじめにあい学校に行けなくなりました。町をさまよっていたら、ある建物を見つけドキドキしながら入ると…。そこは図書館でした。平日に子どもだけでも特に何も言われません。次第に図書館の人や同じく不登校の男の子と交流するようになり、ほのかは自分の居場所を見つけました。 ところがある日、図書館見学のため担任の先生がクラスメイトを連れてくることが分かり…。 図書館には多くの人がやってきます。中には事情を抱えた人も。ほのかは様々な人を見て、関わっていくうちに多様な価値観を知り成長していきます。 この本にはたくさんの児童書が紹介されています。それを読むとさらに自身の世界が広がりますよ。さて、先生とクラスメイトがやって来て、ほのかがどうなったかと言うと…。図書館は利用者の秘密を守ります。
児童書おすすめ(10月3日)
書名 :『だれもしらない小さな家』
著者 :エリナー・クライマー/作 小宮 由/訳 佐竹 美保/絵
出版社 :大日本図書
--------------------------------------------------------------------
自分だけのお気に入りの場所があるって、素敵ですよね。みなさんは、どんな場所を思いうかべますか?
このお話は、大きなマンションにはさまれた、小さな家の物語です。誰も住んでいないその家は、ずっと埃をかぶっています。いろんな人が家を見に来ますが、結局誰も住むことはありませんでした。
小さい家をよくのぞいていたアリスとジェーンは、ある日、ドアに鍵がかかっていないことに気が付きました。
おそるおそる中に入った二人は、家のなかでおうちごっこを始めます。途中で近所に住むオブライアンさんも加わり、三人でクッキー屋さんをしていると、そこに大屋さんが怒鳴りこんで来て…。
とってお
児童書おすすめ(9月26日)
書名 :『ナージャの5つのがっこう』
著者 : キリーロバ・ナージャ/ぶん 市原 淳/え
出版社 :大日本図書
--------------------------------------------------------------------
ロシア生まれのナージャは、小学1年生の女の子。両親の転勤をきっかけにイギリス、フランス、アメリカ、日本。5つの学校に通うことになります。
環境が変わるとガラリと変わるものは?」答えは「ふつう」だと大人になったナージャは言います。授業で使うノートや筆記用具、教室の机やいすの並び、お昼ごはんの食べ方など「なんでこんなに違うの?」と驚くことばかり。転校するたびに、今まで「ふつう」だと思っていたことが通用しなくなってしまうのです。不思議だらけの学校生活の中で、ナージャは世の中にはいろんな「ふつう」があって、いい、悪いじゃなく「違い」があるだけなのだと発見します。
皆さんは「多様性」という言葉を聞いたことがありますか。自分の「ふつう」が他の人にとっての「ふつう」ではないと知ることが、多様性を知る第一歩です。一人で、親子で、そしてお友達と一緒に。この本を読めば、多様に広がる世界の扉が開くかもしれません。
児童書おすすめ(9月17日)
書名 :『三つ編み』
著者 : レティシア・コロンバニ/作 クレマンス・ボレ/絵
出版社 :アンドエト
--------------------------------------------------------------------
巷ではインド映画が流行っています。私が観た作品は、善と悪との闘いや差別が描かれており、最後には悪者は滅び、善良な市民は平和を取り戻す話でした。
映画の余韻も覚めやらぬ日、児童室で目が合った本、それが『三つ編み』です。インドにおけるカースト制度の中で、身分による差別と闘う母と娘の長い旅の物語。子どもが学校に行く。大人が就きたい仕事に就く。それがいかに困難なことか。命をつなぐにはどうしたらいいか?二人は神への祈りを礎にした勇気ある行動で、差別を乗り越えていきます。
彼女が捧げた三つ編みは「かつら」として誰かを笑顔にすることでしょう。本を開くと飛び込むピンクのペイズリーは、母スミタの服の柄。それは生命の樹を意味しており、母の強い思いが重なります。