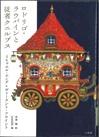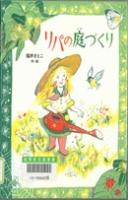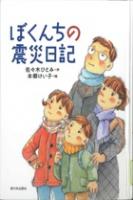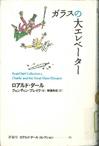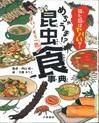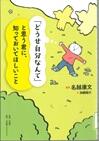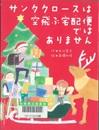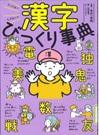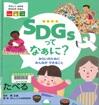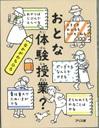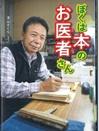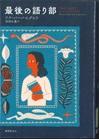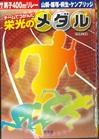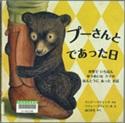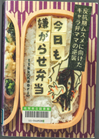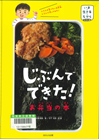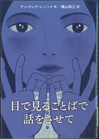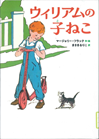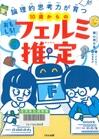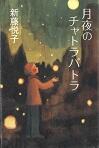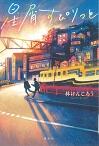小中学生へおすすめ!
児童書おすすめ(2月17日)

書名 : 水のかたち
著者 : 増村 征夫/文・写真
出版社 : 福音館書店
寒い冬も終わりに近づき、少しずつ気温が上がっていくと、雪はしだいに雨に変わっていきます。雨が蒸発すると水蒸気になり、空で雲になった後は、またどこかで雨になります。かたまったり、とけたり、空気に混じったり、私たちの身近な場所でいろいろな形になる「水」について、皆さんはどれくらいご存じですか?
この本は、自然の中で姿を変える水のかたちを、美しい写真で紹介する科学の本です。
水は季節や天気の状況によって雨や雪、霧や露など、さまざまな景色になります。
今日は「天使のささやきの日」です。この記念日に関係する、ダイヤモンドダストとよばれる少し珍しい現象も紹介されています。ぜひ、この本を読んで、外の景色を観察して、「水」の形を探してみてください。
水や気象のふしぎに触れるきっかけにおすすめの一冊です。
児童書のおすすめ(2月10日)
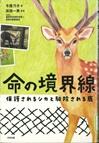
書名 :命の境界線
著者 : 今西 乃子/著 浜田 一男/写真
出版社 :合同出版
近頃、クマによる被害のニュースを耳にすることが多くなりました。クマが山から人の生活圏に現れ、農作物を荒らしたり、人や家畜を襲ったりするため、ハンターたちによって駆除されています。
一方、あまり知られていませんが、クマに限らず、鹿も有害獣として駆除されています。
この本では、奈良公園のシカはマスコットとしてかわいがられているのに、隣の県の滋賀県多賀町の鹿が駆除されているのはなぜか、という疑問を現地の取材を通してわかりやすく説明しています。
また、鹿を実際に駆除するハンターの気持ちを紹介しており、ハンターが野生動物の命と向き合っていることがわかります。
多くの人は野生動物の命を奪いたくないはずです。しかし、野生動物が増加し生態系を崩している主な原因が人間ならば、人間が崩れかけたバランスを立てなおさなければなりません。
この機会に、人と野生動物が共に生きていくためにはどうしたらいいのかを考えてみませんか。
児童書のおすすめ(2月3日)

書名 : ピーチとチョコレート
著者 : 福木 はる/著
出版社 : 講談社
ありのままの自分でいることは、案外と難しいものです。
中学生の萌々は、太っていることがコンプレックス。自信のなさから、笑われる前に笑わせてやれと、おどけたキャラを演じています。けれど言葉と気持ちがバラバラで、本音を言えない辛さも感じていました。
そんな萌々が「人生、変わるよ?」と気になる言葉で誘われて、習い始めたのはヒップホップのラップ教室。
そこには学校で孤立しているクラスメイトの莉愛もいて、二人は次第に親しくなります。ミックスの莉愛は、チョコレート色の自分の肌が好きなのに、いつも隠すようにフードを目深に被っていました。
二人がそれぞれのコンプレックスを乗り越えて、「ルッキズム(外見至上主義)の墓たてろ!」とパワフルに歌う、文化祭のラップバトルは圧巻です。
ずっと反対側にあると思っていたポジティブとネガティブ。最後に萌々がたどり着いた答えとは?
勇気をくれて、心に響く物語です。
児童書のおすすめ(1月27日)
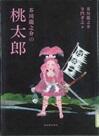
書名 : 芥川龍之介の桃太郎
著者 : 芥川 龍之介/文 寺門 孝之/画
出版社 : 河出書房新社
みなさんは桃太郎が鬼退治に行った理由を思い出せますか。悪い鬼がいたから、財宝を貯めこんでいたから……実は、本によってその理由はさまざま。ほかにも小さな違いはあるけれど、桃太郎がお供を連れて鬼を退治するという大筋は同じ。こうした話のわずかな空白を利用して、芥川独自の桃太郎像が生まれています。
さて、この本で桃太郎が鬼退治に行く理由は「仕事に出るのがいや」だったから。お爺さんもお婆さんも、なまける桃太郎を追い出したくて出陣の支度を手伝います。
よこしまな考えをもった桃太郎とは逆に、平和を愛する鬼たち。討伐後、桃太郎は平穏な日々を送ったでしょうか。鬼たちは変わらず平和を愛したでしょうか。
決して「めでたしめでたし」では終わらない『芥川龍之介の桃太郎』。本当の鬼とは何か考えるとき、私たち人間の在り方についても見つめなおさなければなりません。
児童書のおすすめ(1月20日)
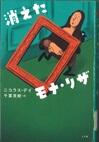
書名 : 消えたモナ・リザ
著者 : ニコラス・デイ/作 千葉 茂樹/訳
出版社 : 小学館
1911年8月21日、フランスのルーブル美術館から「モナ・リザ」が盗まれた!犯人はその日、美術館に忍び込んだのではない。前日、そこに残ったのだ。
大胆不敵な犯罪、異常なコレクターが犯人なのか?それとも「モナ・リザ」を熱烈に愛する者の仕業なのか?いろいろな憶測が飛び交い、世界中から注目が集まる中、犯人は捕まえられなかった。
そして約2年後、事件は急展開を迎える。「モナ・リザ」はルーブル美術館に戻ってくることになった。それもとてもいい状態で…。
一部の人にしか知られていなかった「モナ・リザ」は、盗難そして返還されたことによって、世界的に有名な作品となった。この小説はその経緯と背景、レオナルド・ダ・ヴィンチの人生を織り交ぜながら描いたノンフィクションである。
児童書おすすめ(1月13日)
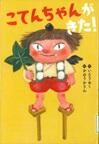
書名 : こてんちゃんがきた!
著者 : いとう みく/作 かのう かりん/絵
出版社 : 理論社
転校生のこてんちゃんは、着物姿のおかっぱ頭に烏帽子をかぶり、手には葉うちわを持って、上履きではなく一本歯下駄を履いています。さらに、その背中にはなんと羽が生えていたので、クラスのみんなは変なのと思います。
しかし、こてんちゃんはマイペース。先生の話はちっともきかず、授業中に「おなかがすいた」と言ってしまいます。その一方で、走りにくい下駄を履いているのに、かけっこで1番になったり、楽しくなると踊ったり、きれいなお母さんが授業参観に来てくれて嬉しそうだったりする様子も。そんな素直で天真爛漫なこてんちゃんと過ごすうちに、誰もこてんちゃんを変だと思わなくなりました。
かのうかりんさんが描くこてんちゃんが魅力的で愛らしく、人と違っていてもいいんだよ、と安心させてくれる一冊です。
児童書のおすすめ(12月23日)

書名 : やってみた!研究イグノーベル賞
著者 : 五十嵐 杏南/著
出版社 : 東京書店
みなさんは、イグノーベル賞という賞を知っていますか?ノーベル賞ではありません、“イグ”ノーベル賞です。この賞は「人を笑わせ、その後、考えさせる」研究や実験に贈られる賞です。
例えば、ワニが鳴き声を出す仕組みを調べるためにヘリウムを吸わせた実験。ワニの声が変わったことで、ワニは人と同じ仕組みで声を出していることがわかりました。
ほかにも、バッタの脳の動きをみるために映画を見せる実験、コーヒーをこぼさずに歩く方法の研究など、受賞した実験や研究は一見おもしろおかしいものばかりです。
しかし、ただ笑えるだけではなく、様々な分野で実際に役立っている研究もたくさんあるのが、イグノーベル賞のすごいところです。ちなみに、日本人は2024年まで18年連続で受賞しているそうです。
紹介されている研究者たちのようにユニークな視点で物事を見てみると、思いがけない大発見で世界を変えることができるかもしれませんね。
児童書のおすすめ(12月16日)
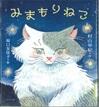
書名 : みまもりねこ
著者 : 村山 早紀/作 坂口 友佳子/絵
出版社 : ポプラ社
この物語は、一匹のおばあさん猫と女の子の絆のお話です。
命の終わりが近づいてきたおばあさん猫の唯一の気がかりは、いつも寂しそうに泣いている女の子のこと。自分の命が終わる直前に、あの子のそばに居たいと星に願いました。願いが叶った猫は、死後、透明な見えない猫になります。
女の子は猫の死を知って悲しみますが、その夜、女の子の夢の中で猫が語りかけます。『ずっとそばにいますからね。みえないけれど、いっしょなの。だから、なかないで』と。
それから女の子は泣かなくなりました。いつも傍には見えない猫がいると信じていたからです。そして、女の子は成長し、大人になった彼女のもとに現れたのは…。
いつも寂しそうにしている女の子に母のように寄り添う猫。柔らかなタッチで描かれる風景の中で、ページいっぱいに描かれる夜空の星はずっと眺めていたいほど印象的です。
種族と時を超えた、大きな愛に心が温かくなる一冊です。
児童書のおすすめ(12月9日)

書名 : こうして、ともにいきている
著者 : 多屋 光孫/作
出版社 : 汐文社
だれかと同じ場所で同じものがほしくなったとき、あなたならどうしますか。早い者勝ち?相手にゆずって自分はあきらめる?
この本に出てくる生き物たちが導き出した答えは、わたしたち人間にとって、だいじなことを気づかせてくれます。
たとえば、同じ川にすみ、同じえさを食べるヤマメとイワナの場合、ヤマメは水の温かいところで、イワナは冷たいところでえさをとります。争わず、ともに生きていくためのじょうずな方法がそこにはあるのです。
ほかにも、「なるほど」と感心する方法でともに生きている自然界の生き物たちが、生命感あふれるダイナミックな色彩とタッチで描かれています。
そして、最後に登場するのは…。
果たして、「ともに生きるということの大切さ」を忘れた生き物の未来はどうなるのでしょう。また、最後のページで投げかけられた問いに、みなさんはどう答えますか。
児童書のおすすめ(12月2日)

書名 : 雪娘のアリアナ
著者 : ソフィー・アンダーソン/作 メリッサ・カストリヨン/絵 長友 恵子/訳
出版社 : 小学館
身体が弱りひとりで農場を営めなくなった祖父と暮らすため、両親と北の山村に越してきたターシャ。ターシャは、以前住んでいた海辺の町で起きたある事件のせいで人と関わることをひどく恐れるようになっていて、村に来て3か月経った今も友だちがいません。大好きな祖父と両親との農場の生活は楽しいけれど、ターシャはいつも孤独を抱えていました。
初雪の日、ターシャは雪で少女の像をつくり「友だちになって」と強く願います。すると雪像に魂が宿り、ターシャは毎晩農場を抜け出し雪娘アリアナと楽しい時間を過ごすように。「アリアナとずっと一緒にいたい」とターシャは願いますが・・・。
ロシアの民話「雪娘」をモチーフにした物語です。春になれば雪娘は消えてしまいます。けれど、アリアナと一緒にい続ける限り厳しい冬が続き、祖父はどんどん弱っていきます。ターシャはどうするのでしょうか。
ターシャと周囲の人々が互いを思いやる優しさにあふれたお話です。
児童書のおすすめ(11月25日)

書名 : たまごのはなし
著者 : しおたに まみこ/作
出版社 : ブロンズ新社
表紙に鎮座するのは、手を組み絶妙な表情でこちらを見つめるたまご。この物語の主人公です。
長いことキッチンでじっと動かずに転がっていたたまごは、ある日突然立ち上がってみることにしました。頭を一口かじってみたことがきっかけで仲間になったマシュマロと、たくさんの初めてを経験します。「当たり前」を押し付けてくる植木鉢の口にテープを貼ってみたり、気ままなたまごたちを羨む、「大事な仕事」がある時計の電池を抜いてみたり。そうすれば仕事をせず休めるから、というたまごの言い分が辛口で爽快です。
長い間、転がっていて動く素晴らしさに気付いたばかりのたまごに先入観なんてものはありません。本当に困ったたまごだとマシュマロが言うように発言や行動には少し毒があるけれど、その哲学にはハッとさせられる大切なことが詰まっています。
ほぼ鉛筆で描かれた薄暗い絵の中で繰り広げられるたまごたちの不思議な日常を、あなたも覗いてみませんか?
児童書のおすすめ(11月18日)
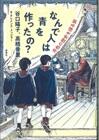
書名 : なんで人は青を作ったの?
著者 : 谷口 陽子/著、髙橋 香里/著、クレメンス・メッツラー/画
出版社 : 新泉社
「青色」は好きですか?
目にも涼しげな青は、晴れ渡った空や浮世絵に波とともに描かれた海のイメージがありますが、かつて絵の具の材料であるウルトラマリンブルーという「青色」1グラムは、「金」1グラムと同じ価値だったのだとか。
この本では、中学1年生の蒼太郎と律が、「青」という色が貴重だった謎について、人類が青色を手に入れた再現実験に挑戦しながら解き明かしていきます。2人のサポート役は骨董店の店主で元大学教授のちょっと変わった化学者、森井老人。ヴェルディグリ、スマルト、エジプシャンブルー、プルシアンブルーなど「青」にもいろいろありますが、それぞれの「ブルー」の原料や素材、作られた方法はどのようなものだったのでしょう。2人の実験は、壮大なブルーの歴史を巡る旅となり、やがてこの経験は少年たちを少しだけ成長させたようです。
ぜひ、みなさんも「青」を探す旅に出ませんか。
児童書のおすすめ(11月11日)

書名 : すべての愛しきLifeへ
著者 : くすのき しげのり/著
出版社 : 瑞雲舎
物語の舞台は、小さな町の外れにある「Life」という店。そこは普通の店と違い、働く人もいなければ売りものがあるわけでもありません。店を訪れる人が誰かに使ってもらいたいものにメッセージを添えて置き、代わりに誰かが置いていったものを持って帰ります。そうして誰かの大切な想い出が、次の誰かの幸せへと繋がっていきます。
そんな「Life」には、子どもから大人までさまざまな人々が訪れます。最愛の人との別れを経験した人も、夢に向かって進む人も、「Life」での交流を通して絶望や迷いの中から希望を見出し、前を向いて一歩を踏み出します。
人は互いに支え合いながら生きていることを実感させられる一冊です。
「Life」を舞台にした物語は他にもあります。絵本の『Life』と『Love Letter』もあわせて読んでみてください。「Life」の感動的な世界をより深く味わうことができます。
児童書のおすすめ(11月4日)

書名 : コクルおばあさんとねこ
著者 : フィリパ・ピアス/作 アントニー・メイトランド/絵 前田 三恵子/訳
出版社 : 徳間書店
子どものときに読み、大人になっても、もう一度読み返してほしい、この本はそんな物語です。
主人公は、風船売りのコクルおばあさん。アパートのてっぺんの部屋のくらしは大変だけど、窓からの見晴らしはいいし、はね窓から飼い猫のピーターが大好きな屋上にも出られるので幸せでした。
ところがある日、ピーターが家出をしてしまいます。ピーターに何があったというのでしょうか。
悲しみと心配で、やせて軽くなってしまったおばあさん。風の強い日に売り物の風船ごと、空に舞い上がってしまいます。
スリル満点の空の旅は、物語一番の読みどころ。おばあさんと一緒に、煙突が並ぶロンドンの街を見下ろし、空を旅する気分が味わえます。
気のどくだと思われることが嫌いで、困っていても人を頼らないコクルおばあさん。はたしてピーターと再会できるのでしょうか。何とも意外な結末が待っています。
猫がつなぐ不思議な出会いの物語。
児童書のおすすめ(10月28日)
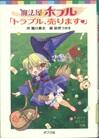
書名 : 魔法屋ポプル「トラブル、売ります♡」
著者 : 堀口 勇太/作、玖珂 つかさ/絵
出版社 : ポプラ社
幻夢界、魔界、天界。この本には、私たちが住む世界以外の様々な世界が登場します。
主人公は、幻夢界で魔法ショップを営む、ダメ魔女のポプル。ある日、強力な魔術師ルルゾ・ラルガスが目の前に現れ、仕事を紹介してもらう約束をしたことが波乱の幕開けとなります。ポプルはなんと魔法を失敗し、脱出不可能な牢獄に1万2000年前から閉じ込められていた大魔王たちを、幻夢界に呼び戻してしまうのです。どうにかして、ラルガスとともに大魔王たちをもう一度封印する作戦を考えることに。
勇敢に戦いを繰り広げる中で、ポプルは何度も挫折を味わいます。しかし、自分で発明した斬新でユーモアいっぱいの魔法道具を巧みに使い、最後まであきらめずに立ち向かっていきます。
あなたは今、「これだけはいつか絶対かなえたい」という夢はありますか?自分にとって大切な夢を持つ皆さんの背中を後押ししてくれる、魔法屋ポプルシリーズ第1巻です。
児童書のおすすめ(10月21日)

書名 : データリテラシー入門
著者 : 友原 章典/著
出版社 : 岩波書店
みなさんは、「データリテラシー」という言葉を知っていますか。データリテラシーとは、一般的にデータをきちんと解釈し活用出来る能力のことと言われています。みなさんも新聞やテレビで、表やグラフなどの統計データを目にする事が多いのではないでしょうか。
この本には、章ごとに現代社会が抱える課題などについてのデータを紹介しながら、その課題のデータを読み解く上で気を付けるべき点などが書いてあります。
同じデータでも、見せ方が違うだけで読み手の持つ印象が変わってくることがあります。そのようなときに、しっかりとデータを読み解くための心構えとして、読んでみてください。
佐賀県でも「さが統計情報館」というウェブサイトで、たくさんの統計データを公開しています。この本を読んで、たくさんのデータに触れてみませんか。
さが統計情報館(別ウィンドウ)もあわせてご覧ください。
児童書のおすすめ(10月14日)

書名 : もしもミツバチが世界から消えてしまったら
著者 : 有沢 重雄/著 中村 純/監修
出版社 : 旬報社
もしもミツバチが世界から消えてしまったら、どんな困ることがあるでしょう? すぐに思い浮かんだのは、ハチミツが食べられなくなるということ。「もう一生食べられませんよ。」なんて言われたらそれは残念です。
それから、ミツバチには花粉を運ぶという重要な役割があります。花はミツバチに花粉を運んでもらい、ミツバチは花からミツ(食べ物)をもらうという、お互いの利益になる関係がなりたっているそうです。ミツバチのおかげで育った植物は、やがて私たち人間や動物たちの食べ物になったり、道具の材料になったりと欠かせないものになります。
そんな大事な役割をもつミツバチも、自然環境の変化で減少している恐れがあるそうです。「知らないものは守れない」と、この本には書かれています。守るために、まずは知ることからはじめましょう。
児童書のおすすめ(10月7日)
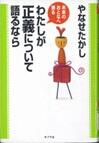
書名 : わたしが正義について語るなら
著者 : やなせ たかし/著
出版社 : ポプラ社
みなさんは、家族や友達と喧嘩をしてしまうことはありませんか?他にもテレビで、外国の戦争のニュースを見たり聞いたりすることがありますよね。こういった争いが起きる理由って何でしょう?
私は子どもの頃、弟とおやつの配分でいつも喧嘩をしていました。理由はそれぞれだと思いますが、お互いに自分が正義で、相手が間違っていると思い込んでいるところから争いが起きてしまう気がします。
この本はアンパンマンの作者である、やなせたかしさんが思う、正義について書かれています。アンパンマンには悪役としてバイキンマンやドキンちゃんが出てきますが、2人とも敵とはいえ、どこか憎めないキャラクターですよね。なぜそのような描き方をしているのか、また、なぜアンパンマンが自分の顔を食べさせてあげるのか、実はそこにやなせさんが考える正義の答えがあります。
何でも白黒つけたくなるあなた、ぜひ読んでみてください。
児童書のおすすめ(9月30日)
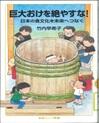
書名 : 巨大おけを絶やすな!
著者 : 竹内 早希子/著
出版社 : 岩波書店
日本の食文化に欠かせない味噌や醤油、日本酒。これらを作ったり保存したりするのに欠かせないもの、それは木おけ。歴史のある蔵元には古い大きな木おけがいくつも並んでいて、100年以上使われているものもあるんだそうです。
ところが今、木おけを作ったり、修理をしたりすることができる職人が少なくなってしまい大ピンチ。このままでは日本中の味噌、醤油、日本酒などが今までのように作れなくなるかもしれません。巨大おけを守るために、味噌や醤油の蔵元同士が協力して、おけの作り方を伝承したり、林業家が材料となる木を育てたりしています。
伝統を守ることの難しさと、職人の技を受け継いでいくことの厳しさに驚くとともに、巨大おけを絶やさないために努力を続ける木おけ職人や、蔵元の人々に感謝します。
味噌汁を飲むとき、醤油をかけるときに、“おけ”のことも思い出してください。
児童書のおすすめ(9月23日)

書名 : あなたの言葉を
著者 : 辻村 深月/著
出版社 :毎日新聞出版
「あのときなんと言えば正解だったのだろう」「いつの間にか自分の本音や、選びたかった選択が自分でもわからなくなってしまった」
そんな気持ちになったことがあるあなたにぜひ出会ってほしい本です。作者の辻村深月さんは、まるですぐ隣にいるかのように、あなたに優しく、そして、まっすぐに語りかけてくれます。「『自分の言葉』は、無理にのみこむ必要もなければ、同じように口に出すことを強制されるものでもありません。」「″空気″の中に自分の気持ちを埋もれさせたり、『思うこと』にブレーキをかけたりしないで…。」と。
「あなたの言葉」がいつか胸からあふれて、あなたの味方になってくれますようにという、温かい願いがちりばめられたこの一冊。「ぜひ読んで!」と大人が強くすすめると、辻村さんの思いと少し離れてしまいそうなので、「出会ってほしいな」「目をとめて手に取ってくれるといいな」という気持ちで、そっと紹介します。
児童書のおすすめ(9月9日)

書名 : 捨てないパン屋の挑戦
著者 : 井出 留美/著
出版社 : あかね書房
日本では、1年間に400万トン以上の食品が廃棄されています。これは私たち一人ひとりが、おにぎりを毎日1個捨てていることになる量です。環境のことを考えても、食品ロスは大きな社会問題です。
パン屋に生まれた田村さんは、どうして捨てないパン屋になったのでしょうか。子どもの頃はパンが嫌いだった田村さん。しかし、実家のパン屋を継いでからは、フランスまでパンの修業に行くほどになりました。そして、まき窯で天然酵母を使ったパンのみを作るようになり、売れ残ったパンを捨てることがなくなったのです。材料や販売方法など試行錯誤の末に、やっと捨てないパン屋になることができました。それはとても長い道のりでしたが、必要な選択でした。
パン屋だけではなく飲食店や販売店、家庭からも日々食品が廃棄されています。これは、私たちみんなが向き合っていかなければならない問題です。食品ロスについて、考えるきっかけにしてほしい本です。
児童書のおすすめ(9月2日)

書名 : 子どもにウケる将棋超入門
著者 : 創元社編集部/編
出版社 : 創元社
皆さんは将棋にどんなイメージを持っていますか?多分、多くの人が難しそうだと思っているのではないでしょうか。
ですが、この本を読んだら、そのイメージも一気に無くなります。将棋を全く知らなくても、丁寧な解説付きなのですぐに将棋を楽しめます。
将棋は、全部で40枚の駒から成り立つゲ―ムです。そのうち、玉将と王将、飛車、角行、金将、銀将、桂馬、香車、歩兵と呼ばれる8種類の駒に分けられます。盤に並べた駒を2人で交互に動かし、相手の王さまの駒を取ると勝ち、取られたら負けです。
この本では、将棋の打ち方や対局の仕方、プロの棋士等について詳しく書かれています。練習ができる棋譜も付いていますので、何回でも楽しむことができます。
最初は、家族や友達と始めてみるとより面白いと思います。ぜひ、挑戦してみてください。
児童書のおすすめ(8月26日)
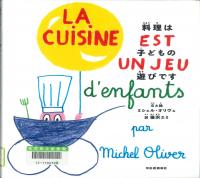
書名 : 料理は子どもの遊びです
著者 : ミシェル・オリヴェ/文と絵、猫沢 エミ/訳
出版社 : 河出書房新社
色鉛筆で描いたようなカラフルな絵が散りばめられたこの本は、フランスで60年以上読み継がれている料理本です。
フランス料理は難しいというイメージを持つ人もいるかもしれません。しかし、この本を読めばタイトルのとおり、「子どもの遊び」のように、簡単で楽しくおいしいフランス料理を作ることができます。
レシピだけでなくフランスと日本の食材や道具のちがいなどの豆知識が書いてあるところも見どころです。本格的なフランス料理のルセット(作り方)がたくさんの絵でやさしく説明されているので、料理をしない人でもまるで絵本のように楽しむことができます。
ページをめくるたびに色とりどりの食べ物を見ていると、あなたもきっと料理をしたくなってきますよ。
児童書のおすすめ(8月19日)

書名 : 恐竜がくれた夏休み
著者 : はやみね かおる/作 武本 糸会/絵
出版社 : 講談社
もし、タイムスリップしてきた恐竜とひと夏を過ごすとしたら、みなさんはどんな日々を送りますか?
主人公の美亜は、夏休みに同じ夢を連続で見るようになります。それは、夜の学校のプールで恐竜が泳ぐ夢。なぜそんな夢を見るのか、その理由を探るため、友人3人と夜の学校に現れるという恐竜のうわさについて調べます。
そのうわさの正体は、なんと現代にタイムスリップしてきた本物の恐竜、ロロだったのです。はじめは戸惑う美亜たちでしたが、元の時代に帰りたがるロロのために、手がかりをともに探すことになります。その中で、地球の未来について知り、美亜たちはとある作戦を立てます。
ロロと関わる中で生じる、美亜たちの関係性の変化や成長も物語の見所です。
なぜロロは現代にやって来たのか、美亜たちが立てた作戦とは、現代にタイムスリップしてきたロロと、小学生グループのひと夏の物語です。
児童書のおすすめ(8月5日)
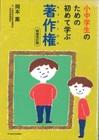
書名 : 小中学生のための初めて学ぶ著作権
著者 : 岡本 薫/〔著〕
出版社 : 朝日学生新聞社
著作権とは何でしょう。
よく耳にしますが、実際には、理解していると自信を持って断言できる人は少ないのではないでしょうか。
著作権とは、「自分で作ったものを勝手に使われない権利」と言うことができます。
この本では、著作権の対象となるものや、誰が著作権を持つのかなど、著作権について身近な例も交えてわかりやすく説明されています。また、著作物の作成・利用時に気をつけるべきことや、著作物を無断で使われないための予防方法なども解説されています。
現代では、インターネットや電子機器が広まり、誰でも物を「作る人」と「使う人」になることができます。そのため、著作権に関する理解を深めることが重要です。ぜひ、自分自身が「著作権を持つとしたら、他者の著作物を利用するとしたら」という見方で読んでみてください。
児童書のおすすめ(7月29日)

書名 : 6days遭難者たち
著者 : 安田 夏菜/著
出版社 : 講談社
「冒険とは、死を覚悟して、そして生きて帰ることである」。
元登山部の美玖、近所に住む亜里沙、そのクラスメイトの由真。薄いつながりの同級生3人は一緒に低山登山にでかけることに。ロープウェイを利用したお手軽日帰り登山のはずでしたが、山頂到着後ほんの少しの油断から誤った道に入り込み、山をさまようことになります。3人が登山に挑戦した理由は様々。その背景をからめながら美玖、亜里沙、由真それぞれの視点でその時の状況が描写されます。
判断ミスが命の危険に直結する登山。ひとつひとつは小さなことなのに、山での遭難はこうして起こるのかとぐっと引き込まれ思わず一気読みしてしまう作品です。冒頭の一文は冒険家植村直己氏が残した言葉で中表紙をめくった1ページ目に書かれています。この言葉の重みを感じ、そしてこの言葉が物語にどんな関わり方をするのかに注目しながら、ぜひ読み進めてください。
巻末の「遭難防止五か条」も必読です。
児童書のおすすめ(7月22日)
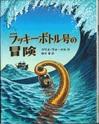
書名 : ラッキーボトル号の冒険
著者 : クリス・ウォーメル/作、柳井 薫/訳
出版社 : 徳間書店
両親に叱られて家を飛び出したジャックが家出先に選んだのは船。ところが運悪く嵐が船を襲い、ジャックは絶海の孤島に打ち上げられてしまいます。
無人島に見えたその島には、長い間ひとりぼっちで本を読んで過ごしていた男ロビンソンと、巨大なカメが住んでいました。
家へ帰りたいと願うジャックに、ロビンソンは手紙を書くことを提案します。ジャックは文字を習っては、手紙をビンに入れて海に流し、助けを待ちわびます。
そんなある日、島に埋められた骸骨の手に握られていた謎の紙きれが、海賊の宝のありかを示していることに気がつきます。
嵐に始まるジャックの海の大冒険。果たしてジャックは宝を探し出し、無事に家へ帰りつくことができるでしょうか。海賊、魔女、しゃれこうべ、宝の地図に謎の呪文まで。奇想天外な物語の展開に、ページをめくる手が止まらない一冊です。
児童書のおすすめ(7月15日)
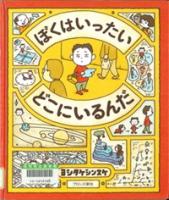
書名 : ぼくはいったいどこにいるんだ
著者 : ヨシタケ シンスケ/作
出版社 : ブロンズ新社
おつかいを頼まれた「ぼく」は、おかあさんが描いた地図がさっぱりわからなくて迷ってしまいました。しかし、みーちゃんのママは目的地をわかるようにと地図にいろいろと描き足してくれて、無事におつかいをすることができました。「ちずがあれば、いまじぶんがどこにいるのかがわかる」「なにかを絵にしてわかりやすくしたものがちずだとしたら…」「じぶんのためだけのちずを、じぶんでつくってもいいよね」と「ぼく」は言います。
自分の部屋の地図やクラスの中での人間関係の地図、今の自分の気持ちの地図。また、未来の地図など発想を膨らませてみると、いろいろな面白い地図を作って観察し、楽しむことができます。物事の仕組みや関係性と問題点、あるいは自分の好奇心など、目に見えない事がらを見えるように(可視化)することで、今や未来が見えてくるし、理解や解決しやすくなったりもします。もうすぐ夏休み、みなさんもオリジナル地図を作ってみませんか。
児童書のおすすめ(7月8日)

書名 : 草のふえをならしたら
著者 : 林原 玉枝/作 竹上 妙/画
出版社 : 福音館書店
物語に登場するのは一風変わった植物の笛です。はじめに出てくるのはねぎの笛。まこちゃんがねぎの青いところをちぎって、ストロー状にして息を吹き込むと、“ブイッブイブイッブブブウ”と音が鳴りました。その不思議な音色に誘われてやってきたのはうすいピンク色のぶた。ぶたはまこちゃんの料理のお手伝いをしたいというのですが…。
その他にもさくらの花びらやささの葉・どんぐりなど、ユニークな笛が登場します。笛が奏でる音色が結ぶ、こどもたちと動物たちとの楽しい交流を描いたおはなしです。
物語の中にはたくさんの植物が出てきます。笛の吹き方も書かれているので、本を読みながら実際に音を鳴らして楽しむこともできます。みなさんの周りにもたくさんの植物がありますね。その植物を笛にして音を鳴らしてみましょう。何か不思議な出来事が起こるかもしれませんよ。
児童書のおすすめ(7月1日)
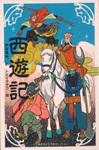
書名 : 西遊記
著者 : [呉 承恩/作] 武田 雅哉/訳 トミイ マサコ/絵
出版社 : 小学館
世界中でさまざまな作品にリメークされている『西遊記』。三蔵法師とともに孫悟空・猪八戒・沙悟浄が仏教の経典を求めて天竺へ向かい、そして帰ってくるという“行きて帰りし物語”です。
『西遊記』は、中国の宋(10~13世紀)の時代に、もとになった旅行記『大唐西域記(だいとうさいいきき)』を「講談」「お芝居」などの形に発展させ、親しまれていました。
観客の前で語るわけですから、とにかく盛り上がり重視!どんどん話を大げさに、面白おかしく脚色していきます。『西遊記』に登場するのが自分勝手でハチャメチャな人ばかりなのも、面白さを追求した結果なのかもしれませんね。
『西遊記』の中で私が好きなのは、不思議な霊力を持つ「人参果」を盗み食いしたお話。師匠の三蔵にバレそうになって、悟空は八戒と仲間割れ、挙句の果てには人参果の木を根こそぎ倒してしまいます。さてこの先、いかなることにあいなりますやら…。続きはぜひ、本を読んでお楽しみください。
児童書のおすすめ(6月24日)

書名 : 働く現場をみてみよう!わたしたちが寝ている時間の仕事
著者 : パーソルキャリア株式会社“はたらく”を考えるワークショップ推進チーム/監修
出版社 : 保育社
世の中には、私たちが寝ている時間帯にお仕事をしている人がいます。実際にその現場を見ることができる機会はなかなかないのではないでしょうか。
急に具合が悪くなったときに診てくださる医師や看護師のように、24時間体制で働く人たちがいます。私たちがお昼の間に楽しく利用するテーマパークは、点検や修理を行う整備士、安全で清潔な環境を保つ清掃員など、たくさんの方の支えがあって成り立っています。表には見えづらい支えがあるからこそ、日頃から安心してスムーズにサービスを利用できるのです。
仕事をしていると、やりがいやうれしいことだけでなく、大変だと感じることもあります。
インタビューのページでは、その仕事の魅力や向いている人など、本音をのぞくことができます。
はっきりとした夢を持っている人も、まだ将来のことはイメージできていない人も、まずは、私たちの前に広がるたくさんの選択肢について知ってみませんか?
児童書のおすすめ(6月17日)

書名 : AIにはない「思考力」の身につけ方
著者 : 今井 むつみ/著
出版社 : 筑摩書房
「いちごのしょうゆをちょうだい」3歳くらいの子どもが言いました。これはどんな意味でしょうか?
この子は「しょうゆ」の存在を知っています。「しょうゆ」は「たべものにかけておいしくするもの」という認識です。「いちごをおいしくするものが欲しい」けれど、その名前を知らない。だから考え、「しょうゆ」という言葉を使って、いちごにかける「コンデンスミルク」を自分なりに表現したのです。このことこそが「ことばの力」と「思考力」で、問題を解決することだと著者は語っています。
私たちは変化の激しい時代に生きています。今ある職業が数十年先にはなくなっている可能性もあるのです。そんな時代を生き抜くために何を身につければいいのか、AIにはなく人間だけにあるものは何なのか、ことばの学びはなぜ大切なのか。認知科学、認知心理学を研究している著者が、自身の著書『親子で育てることば力と思考力』を10代向けに書き直し、やさしく解説しています。
児童書のおすすめ(6月10日)

書名 :まいどばかばかしいお笑いを!
著者 : 赤羽 じゅんこ/作 フジタ ヒロミ/絵
出版社 : 講談社
小学生の天音は、おしゃべりが好きで、家でも学校でもよくしゃべる女の子。
おしゃべりが好きなら落語でも習ってみたら?と、お母さんの知り合いの女性落語家悠々亭若葉さんを紹介してもらいます。
天音は近所の老人ホームで、2か月後に落語の『転失気(てんしき)』を披露することになり、若葉さんに稽古をつけてもらいながら、覚えたことをただ一方的にしゃべるのではなく、相手に伝わるようにしゃべらなければならないことを学び、本番当日を迎えます。
天音の落語は、果たして成功するのでしょうか?最後の「落ち」にも注目です!
巻末には、落語のはじまりや、江戸落語と上方落語の違い、落語の登場人物のくらしなど、ひとくちメモもついています。 物語を楽しみながら、日本文化を学ぶことができる本です。
児童書のおすすめ(6月3日)

書名 : 日本のことばずかん そら
著者 : 神永 曉/監修
出版社 : 講談社
ふと空を見上げてみると空にはたくさんの表情があり、天気や季節、時間帯によって、全く違う顔を見せてくれます。
人々はその空の様子に美しい名前をつけてきました。例えば、晴れを表す言葉だけでも、つゆ晴れや夕晴れ、日本晴れなど様々な呼び名があります。この本では、そのような天気や自然を表す言葉を写真と一緒に紹介しています。
今は雨の季節。たくさんの雨の表情に出合えます。雨の名前を表す言葉はなんと400以上あると言われています。
また、雨かんむりの漢字も350以上あります。その中でも一番画数の多い字は䨻です。 雷が四つ並んだ不思議な漢字は、何と読むのか、どういう意味なのか、本の中で探してくださいね。
この時期、うんざりすることもありますが、雨がどんな風に降っているのか、どんな音がするのか、じっと観察してそれに近い雨の名前を探したり、オリジナルの名前をつけて楽しむのもいいかもしれません。
児童書のおすすめ(5月27日)
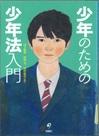
書名 : 少年のための少年法入門
著者 : 山下 敏雅、牧田 史、西野 優花 /監修
出版社 : 旬報社
テレビやネットでは、毎日犯罪のニュースが報道されています。その中では、子どもが起こした犯罪もあります。
罪をおかした子どもがどんな裁判を受け、どんな扱いを受けるのかについては、「少年法」という法律で決められていますが、名前は聞いたことがあっても、詳しい中身は知らないと思います。
この本の監修者の1人、山下弁護士は、子どもたちのための法律が、子どもたちに知らされていないのは問題だと考え、この本を作られました。
「少年犯罪は年々増加し、凶悪化している」という話を聞いたことがあるかもしれません。しかし、実は少年犯罪は2003年以降減少し続けており、凶悪事件(殺人)についても96件(2003年)から52件(2019年)と大きく減少しています。
「犯罪は自分と違う世界で起きている」「法律は自分と関係なさそう」という考えから、「少年犯罪は年々増加し、凶悪化している」というイメージが持たれ、そこから少年法が厳罰化の方向に改正されてきているそうです。
この本を読み終えたとき、少年法についての正しい知識が得られ、皆さんが新しい社会を作る一歩になると思います。
児童書のおすすめ(5月20日)

書名 : ほんとうのリーダーのみつけかた
著者 :梨木香歩/著
出版社 :岩波書店
みなさんが思うリーダーのイメージはどんな人ですか。強そうで堂々としていて、自信満々な人。そういうどことなく強そうな雰囲気の人がリーダーのイメージだと感じる人もいるかと思います。でも、みなさんの中にもそのような雰囲気の人の意見に、流されてしまったことがある人もいるのではないでしょうか。
あなたのほんとうのリーダーは、両親、友達、先生よりもあなたのことを全て知っている。しかも、あなたの味方でいつだってあなたの立場に立って考えてくれる人がリーダーではないでしょうか。
この本の著者・梨木香歩さんが言っています。「いつか、私などの想像もつかない、伸びやかな精神を持つ次世代が現れんことを夢見つつ祈りつつ」と。
あなたの周りにリーダーとなれる人はいませんか。この本の中にリーダーとなれる人物像が書かれています。
児童書のおすすめ(5月13日)

書名 : 作ろう!フライドチキンの骨格標本
著者 : 志賀 健司/著 江田 真毅、小林 快次/監修
出版社 : 緑書房
最近の研究では「すべての鳥は恐竜の子孫」といわれています。みなさんはすでにご存じかもしれませんね。
この本では「”現生恐竜”の代表」とされるニワトリの骨を使って、なぜ鳥が恐竜の子孫だといえるのか、その理由を探ります。
骨の歴史を学び、恐竜とニワトリの類似点を見つけた後は、フライドチキンを「採集」し、骨格標本作りの始まりです。チキンを食べたら満足してしまいそうですが、ここからが本番。薬品処理をしたり、組み立てたり、根気のいる作業が続きます。
骨格標本作りは大変ですが、過去ではどんな姿だったのか、未来ではどう姿を変えていくのか、想像すると、なんだかワクワクしませんか。本を通して、連綿と続く生命の歴史を感じることができますよ。
児童書のおすすめ(5月6日)

書名 : 虫ぎらいはなおるかな?昆虫の達人に教えを乞う
著者 : 金井 真紀/文と絵
出版社 : 理論社
あなたは虫が好きですか?嫌いですか?
虫が好き・嫌いとなる分岐点、ゴキブリが「汚いもの扱い」されているのは実は不当であること、なぜ動物の病院はあるのに虫には病院がないのか、アメンボはあめ玉の匂いがするからアメンボ、日本ほど「虫とり」がポピュラーな国は珍しい…。この本では、昆虫の達人7名の教えによる虫についての実態や意外と思える一面が、ユーモラスにわかりやすく散りばめられています。
達人は「虫が嫌いなのは観察が足りないから」と言い、虫が嫌いな作者の思いも達人と出会うなかで、「知ってから好き嫌いを判断すればいいのに、知らないで嫌いになるのは不当だ」と変化していきます。カニが怖くて嫌いな私は、一つ穴の中でカニとカエルが重なりあい冬眠するほほ笑ましい姿を見つけ、嫌いレベルが少しダウン。知らず嫌いは日々のなかに多々あるけど、「嫌い」なことと上手に付き合うことができるようになれたらいいですね。
児童書のおすすめ(4月29日)

書名 : すこしずつの親友
著者 : 森埜 こみち/著
出版社 : 講談社
一人でいるとさみしい、親友がほしい。そう感じることはありませんか。 この本に登場するのは、今すぐ親友がほしい「わたし」と、すこしずつの親友がいる「伯母さん」です。
この「すこしずつの親友」とは、長い時間を共にして、心を許して話ができる親しい友人のことではありません。
例えばこんな話が紹介されています。海外の空港で、伯母さんは男性にスーツケースをぶつけてしまいました。謝る伯母さんに、彼は眼だけでうなずくように笑います。お互いの気持ちが通じ合った一瞬の出来事でした。伯母さんは彼のことを「すこしずつの親友」だと言います。
短時間の出会いでも、心の交流をしたり、忘れられない思い出になったり、新たな学びを得たりすることができます。あなたが孤独を感じる時、あなた自身の「すこしずつの親友」を思い出してみませんか。
児童書おすすめ(4月22日)
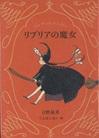
書名 : リブリアの魔女
著者 : 日野 祐希/著
出版社 :アリス館
この本は魔法が使える世界で魔導師を目指している、メノアという女の子の物語です。
メノアは、弟子入り試験をかねていた魔法学院の卒業式を風邪で欠席してしまいました。このままどこにも弟子入りできなければ、魔導師になることができません。いとこのつてを頼りに、伝説の天才魔導師のシェリルの元へ弟子入りを頼みに行きます。 向かった魔導書工房には、美しいけれど、どこかおとぼけたオーラを漂わせている、不思議な魔導師がいました。
しっかりもののメノアと、おとぼけシェリルのでこぼこコンビは、無事に師弟になれるのでしょうか?
メノアは弟子入りの試験のために国の各地を巡り、魔導書の材料を集めてくることになります。旅先では知らないことや初めてのことばかり。不安でいっぱいになりながらも様々な試練を乗り越えていきます。
失敗を恐れずに挑戦することの大切さを教えてくれる物語です。
児童書のおすすめ(4月15日)

書名 :なんてくさいんだ!
著者 :コリーン・ペフ/文 ナンシー・カーペンター/絵 金原 瑞人/訳
出版社 :あかつき教育図書
19世紀、世界一の都市ロンドンでは、人口が増えすぎておしっこやうんちの処理に困り、すべてを川に流した結果、息が詰まるようなひどいにおいがしていたそうです。それでも人々はそのくさくて汚れた水を飲むしかなく、とうとう感染症を発生させてしまいます。
その難題に立ち向かった一人の土木技師がいました。この本の主人公ジョゼフ・バザルジェットです。彼は、川に汚水を流さない新しい下水道の仕組みを設計し、「悪魔の悪臭」ともよばれたにおいと、病の大流行の恐怖から人々を解放しました。水の汚染の克服が、すがすがしい空気と健康的な生活をもたらしたのです。
しかし、ジョゼフの奮闘から百年以上たった今でも、おしっこやうんちのまじった水を飲まざるをえない人たちが、世界に20億人近くいるそうです。
私たちの命を左右する安全な飲み水。蛇口をひねるときれいな水の出る環境は、決して当たり前のものではないのだと気づかされます。
児童書のおすすめ(4月8日)

書名 : わたしは食べるのが下手
著者 : 天川 栄人/作
出版社 :小峰書店
あなたは給食が好きですか?食べることは楽しみですか? この本には、食べることに悩む中学生が登場します。会食恐怖症で給食を完食できない葵、痩せたくて過食嘔吐をくり返す咲子、ムスリムのラマワティ、貧困で給食が頼りのコッペ。彼らは、周囲が悩みを理解してくれないことにも傷付いています。
やがて給食ボイコットを試みた葵と咲子は、栄養教諭の橘川先生に、ならばどんな給食にしてほしいのか要望書を出して、献立も考えてみろと焚きつけられます。この橘川先生は、栄養オタクの変わり者だけど、ルールを押し付けずにみんなが納得する案を探してくれる素敵な先生です。
はたして葵たちの給食改革はうまくいくのでしょうか?
受け身だった葵が、ぐいぐいとみんなを引っ張る存在に変貌していくところも物語の魅力です。食を知り、互いの事情も思いやることで成長していくのです。 食べることは生きること。『食』について考える、この本を読んでみませんか?
児童書のおすすめ(4月1日)
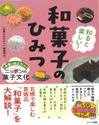
書名 : 知ると楽しい!和菓子のひみつ
著者 : 「和菓子のひみつ」編集部/著
出版社 : メイツユニバーサルコンテンツ
日本の四季を感じさせてくれる和菓子。 春はさくらもちやお花見の団子、夏は涼しげな水ようかんやわらびもち、秋は栗きんとん、冬はぜんざいなど、その季節ごとに味わい楽しむことができます。
普段何気なく食べている和菓子ですが、どうやって誕生したのか知っていますか? 昔は菓子といえば木の実や果物のことを指していました。今でも果物を水菓子というのはその名残です。その後、外国から伝わった菓子が日本独自の和菓子へと進化していったのです。
この本では、和菓子の歴史や種類などの基礎知識から、ようかんやカステラなどの代表的な和菓子のルーツ、全国に伝わる郷土菓子などを紹介しています。 奥深い和菓子の世界を知りたい方におすすめの1冊です。
佐賀県の代表的な和菓子「丸ぼうろ」も紹介されていますよ。
児童書のおすすめ(3月25日)
書名 :ロドリゴ・ラウバインと従者クニルプス
著者 :ミヒャエル・エンデ/作 ヴィーラント・フロイント/作 木本 栄/訳 junaida/絵
小学館
--------------------------------------------------------------------
ロドリゴ・ラウバインは荒野に建つ城に住む、誰もが恐れる盗賊騎士です。
そんな恐ろしいロドリゴの従者になろうと、怖いもの知らずの少年クニルプスはひとりで彼の城をたずねます。
クニルプスは従者になるため、ロドリゴに度胸試しを命じられます。そんなクニルプスの度胸試しが、王さまやお姫さま、お城の魔術師や竜を巻き込んでの物語に発展していきます。
怖いもの知らずで無鉄砲なクニルプスは多くの困難の中、さまざまな感情を学び優しくたくましく成長していきます。
この物語は『モモ』や『はてしない物語』を書いたミヒャエル・エンデの未完成の物語を、ヴィーラント・フロイントが完成させた作品です。
クニルプスだけでなく、エンデの生み出したキャラクターたちはフロイントのもとでどのように成長していくのでしょうか。
少し長めの物語ですが、きっとページをめくる手が止まらなくなるはずです。
児童書のおすすめ(3月18日)
書名 :リパの庭づくり
著者 :福井 さとこ/作・絵
のら書店
--------------------------------------------------------------------
リパはうでのいい庭師です。ある朝、リシュカおばあさんの家にやってきたリパは、美しかった庭が荒れ果てている光景を見て驚いてしまいます。おばあさんに理由を尋ねると、飼い猫のマリーがいなくなってしまって何にも手につかないというのです。そこでリパはおばあさんを元気づけるために、野鳥のシーコルと協力して、庭の手入れをはじめるのですが…。
この本のみどころは、シルクスクリーン(孔版)という種類の版画で描かれた挿絵です。荒れ果てた庭が、よみがえる様子が独特の美しい風合いで描かれており、植物のみずみずしい生命力が伝わってきます。
冬が終わり春の訪れを感じられるようになってきました。みなさんの周りでもたくさんの植物が芽吹いているのではないでしょうか。リパのように植物に触れて、全身で自然の息吹を感じてみませんか?
児童書のおすすめ(3月11日)
書名 :ぼくんちの震災日記
著者 :佐々木 ひとみ/作 本郷 けい子/絵
新日本出版社
--------------------------------------------------------------------
2011年3月11日に発生した東日本大震災から今日で14年。小中学生のみなさんはこの震災について、聞いたことはあるけど詳しくは知らない…そんな人が多いかもしれませんね。震度7の地震をきっかけにした大きな大きな震災でした。
この本は、3月11日からの4日間の物語です。主人公は小学4年生。中学生のお姉ちゃんがいます。地震が発生した時の様子、避難の様子、怖さ、つらさ、悲しさ、切なさ、そして「がんばろう」の気持ち。それらがこの本からは伝わってきます。
物語の主人公とその家族が体験したことのほとんどは、作者が実際に体験したことだそうです。「防災用品を備えるように、“心”も備えて」と、東日本大震災を体験した作者は語ります。この本で“心”の備えをはじめませんか。
児童書おすすめ(3月4日)
書名 :ガラスの大エレベーター』(ロアルド・ダールコレクション5)
著者 :ロアルド・ダール/著 柳瀬尚紀/訳
評論社
--------------------------------------------------------------------
あなたの乗ったエレベーターが天井を突き抜け宇宙まで飛んでいったらどうする?ガラスのエレベーターでチョコレート工場に向かうはずのワンカ氏とチャーリー一家でしたが、なんと宇宙まで飛んでいってしまい…。「ガラスの大エレベーター」はそんな奇想天外なお話です。20巻あるロアルド・ダールコレクションの中の1冊で、大人気で映画化もされた「チョコレート工場の秘密」の続編です。
著者のダールは、子どもたちを寝かしつけるため毎晩いろんなお話をしてあげていました。5人の子どもたちは夢中になり「もっともっと」と先をせがんだそうです。そしてダールは物語を書くようになりました。
ダールの作品は、思いもよらない展開があり、言葉がおもしろく笑いを誘い、そして何より子どものことが大好きだという思いにあふれています。この本を読んであなた自身が自由に想像を膨らませ、ダールの物語の世界を楽しんでください。
児童書のおすすめ(2月25日)
書名 :めちゃうま!?昆虫食事典
著者 :内山 昭一/監修 大串 ゆうじ/絵
大泉書店
--------------------------------------------------------------------
皆さんが好きな料理は何ですか?カレー、お寿司、からあげ?お肉やお魚を使った料理が多いと思います。
この本のテーマは、名前のとおり「昆虫食」です。「虫を食べるなんて気持ち悪い!!」と思うかもしれませんが、実は、虫は1万年前から世界中で食べられています。日本でも、イナゴやカイコなどが食べられているんですよ。
この本は、昆虫料理研究家の作者が、64種類の虫を実際に調理して、味や栄養などを紹介しています。「バッタ入りお好み焼き」「セミのチョコがけ」「スズメバチのサナギと幼虫の串焼き」などのメニューがイラスト入りで紹介されており、とても美味しそうです。アゲハ蝶の幼虫は、ゆでるとミカンの香りがするそうです。興味がわきませんか?
虫は栄養豊富で、少ないエサや水で狭い土地でも育てられることから、SDGsの観点や、これから予想される人口増加による食糧不足を救う方法として、あらためて注目されています。
この本を読むと、虫を見る目が変わると思いますよ。
児童書のおすすめ(2月18日)
書名 :おしごとそうだんセンター
著者 :ヨシタケ シンスケ/著
集英社
--------------------------------------------------------------------
宇宙船が地球に落ちたときのケガで記憶喪失になってしまった宇宙人。生きていくために何かおしごとをしなくてはと「おしごとそうだんセンター」を訪ねます。
「おしごとって何?」「どうやって選べばいいの?」何もかもが初めてで不安でいっぱいの宇宙人に、相談係のおねえさんが優しく働くとはどういうことかを教えてくれます。
ヨシタケシンスケさんならではのユニークな世界観に思わず笑ってしまう44のおしごとは、見開きの右ページにイラストが、そしてページをめくると名前と解説が書かれています。イラストを見て「これはどんなおしごと?」とクイズのように当てっこするのも楽しいかもしれません。
子どもにとってまだ知らないことだらけのおしごとの世界。いつかおしごとするみなさんも「おしごとそうだんセンター」を訪ねてみませんか。「大事な人」のために一生懸命働いてくれている「お父さんやお母さん」の想いも知ることができると思います。
児童書のおすすめ(2月11日)
書名 :作って発見!日本の美術
著者 :金子 信久/著・工作
東京美術
--------------------------------------------------------------------
みなさんは「日本美術」にどんな印象を持っていますか。難しい?暗い?敷居が高い?
日本美術に限らず、美術の楽しみ方は様々ありますが、この本は「まず工作で作ってみよう!」と提案しています。実際に作品を作ることで、技術的なことはもちろん、作者の意図やアイデアがよく分かるのだとか…。
例えば、俵屋宗達画・本阿弥光悦書の《鶴下絵三十六歌仙和歌巻》は、優雅に飛び立つ鶴の群れを和歌とともに表現した名画です。これを工作にすると、金と銀の連続したハンコがかわいい作品になります。私もこの本を参考に実際に工作を作ってみましたが、同じモチーフのハンコが重なったり離れたり、画面からはみ出したりするところに、不思議なリズムを感じました。
そもそも美術は難しいものではありません。工作を通して、日本美術の自由な発想とデザインの魅力を、楽しみながら体験してみてください。作品に触れあなたの心が動いたら、それがアート鑑賞の第一歩です。
児童書のおすすめ(2月4日)
書名 :チョコレートのおみやげ
著者 :岡田 淳/文 植田 真/絵
BL出版
--------------------------------------------------------------------
ニワトリと風船売りの男は、おたがいに大切な相棒。ニワトリはその日の風の向きや強さを男に教え、やさしい男はそれを聞いて風船を売るかどうかを決めていました。風船がたくさん売れた日は大好きなチョコレートをたくさん買っていっしょに食べました。
午後から強い南風が吹きそうなある日のこと、ふとニワトリにいたずらな心が生まれてしまいます。「きょうは風がふかないね」そのひとことでニワトリと男の幸せな毎日がとつぜんこわれてしまいます。男のやさしさに甘え、うそをついたニワトリと風船売りの男の行く末は?
チョコレートは時間やいろいろな出来事を溶かしていく力がある。そんな不思議なチョコレートの魅力に引きこまれてしまいます。実はこれ、「ゆき」と「みこおばさん」の会話からできたお話。やさしい二人にチョコで乾杯!
児童書のおすすめ(1月28日)
書名 :「どうせ自分なんて」と思う君に、知っておいてほしいこと
著者 :加藤 隆行/文 名越康文/監修
小学館クリエエイティブ
--------------------------------------------------------------------
あなたは自分のことが好き?それとも嫌い?友だちにイヤなことを言ってしまった。スポーツが苦手だからカッコ悪い。先生に怒られてばっかり。そんな自分のことが嫌いだったりしませんか?もしそうなら、この本を読んでみると、自分に自信がもてるようになるかもしれません。自分に嫌いなところがあっても大丈夫。この本を書いた加藤さんはこう言っています。「自分はそのままでいいと信じてみませんか?」と。
自分の嫌いなところは、そのままでいいんです。短所は別の見方をすれば長所にもなります。少し考え方を変えれば、嫌いなところも好きになれるかもしれません。その「考え方を変える」やり方を、この本は教えてくれますよ。今の自分を好きになれたら、きっともっと人生は楽しくなるはずです。
「どうせ自分なんて」と思ったことがあるなら、一度この本を読んでみませんか。
児童書のおすすめ(1月21日)
書名 :源氏物語入門
著者 :高木 和子/著
岩波書店
--------------------------------------------------------------------
書店で『源氏物語』のコーナーを見かけ、物語や紫式部の人気の高まりを感じています。平安時代・中期は、十二単や和歌などの文化が花開きました。この時代に書かれた『源氏物語』は、世界で最も古い長編小説といわれ、貴族の暮らしや行事、今に伝わる祭も描かれています。
『源氏物語』が書かれた時代は、和歌を送り好きな人に気持ちを伝えていたので上手な和歌を作ることは重要でした。『源氏物語』には約800首もの和歌が詠まれ、平安時代・後期には「『源氏物語』を読まない歌詠みは残念」といわれ、『源氏物語』は和歌の教科書にもなりました。
『源氏物語』は、一条天皇に献上するために書かれた物語ですが、書き始めた時から貴族の間で物語が面白いと話題になりました。光源氏のライバルへの対抗心や友情などは、いつの時代にも共通することで、1000年経った今も共感をもって読み続けられています。紫式部が書いた平安貴族の物語を読んでみませんか。
児童書のおすすめ(1月14日)
書名 :保健室には魔女が必要
著者 :石川 宏千花/作 赤/絵
偕成社
--------------------------------------------------------------------
魔女たちは現在「七魔女決定戦」のまっさい中。勝者の条件は、自分が考案した「おまじない」を世の中にたくさん定着させること。普段は人と同じように生活し人間社会に溶け込んでいる魔女たちですが、七魔女に選ばれるため、あの手この手で自分のおまじないを広めようと日夜活動しています。
《満ち欠けの扉》こと人間名「弓浜 民生(ゆみはま たみお)」も七魔女決定戦に参加中の魔女。中学校の養護教諭として、保健室を訪れる中学生の悩みを聞き、それに合うおまじないを作り伝授(でんじゅ)することで、おまじないの定着を狙(ねら)っています。
《満ち欠けの扉》が人としての職業に養護教諭を選んだのは七魔女になるためだけではありません。こどもたちには魔女のおまじないが必要だと思ったから。もしかしたらあなたの学校の保健室の先生も、そんな優しい魔女だったりするかもしれませんね。
友だちへの不満、家族へのイライラ、容姿へのコンプレックス、特別への憧れ・・・。今悩んでいる人におすすめの連作短編集です。
児童書のおすすめ(12月24日)
書名 :サンタクロースは空飛ぶ宅配便ではありません
著者 :市川 宣子/作 高橋 和枝/絵
ポプラ社
--------------------------------------------------------------------
今年、1年生の間に流れているうわさ。「4年3組の黒須三太くんにおねがいの手紙を書けば、クリスマスにはほしいものがもらえる」らしい。
そんなわけあるかよ…とうんざりする三太ですが、くつ箱に届く手紙を捨てるわけにもいかず、偶然見つけた「サンタクロースあて」と書かれた赤いポストに入れてみることに。すると、赤鼻のトナカイ、ルドルフが現れて、今年のサンタ役に三太が選ばれたと話すのでした。
続々と増えていく手紙と、クリスマス本部から送られてくるプレゼントのチェック。トナカイに乗る練習もしなければならず、三太は大忙しです。
そんな中、手術の前にサンタさんに会いたいとの願い事が舞い込みます。これはなんとかしてあげたいと、ルドルフは行方不明のサンタクロースを探しに行ってしまいます。
トナカイ不在のまま、友人のたくやと和人とで配達をすることになった三太。クリスマス嫌いな三太が奮闘する姿をぜひ最後まで見届けてください。
児童書のおすすめ(12月17日)
書名 :闇に願いを
著者 :クリスティーナ・スーントーンヴァット/著
静山社
--------------------------------------------------------------------
願ったことが実現するとしたら、何を願いますか。もしあなたが特別な力を手に入れたら、どのような行動をとるでしょうか。
物語の舞台・チャッタナーの住人は、街を治める総督のことをとても尊敬しています。総督が、特別な力を使って、大火で灰の街になったチャッタナーに光をもたらしたからです。しかし総督は、自分にとって価値がある人にしか光を与えるつもりはありませんでした。
主人公のポンは刑務所で生まれたため、総督が作った法律により、13歳まで出所できません。13歳になるのを心待ちにしていたポンですが、総督の考えを知り、刑務所から逃げ出すことにしました。
たどり着いた村で、ポンはひとりの老僧と出会います。自分の願いは、追手から逃げきり、自由になることだと思っているポン。老僧はそんなポンに、進むべき道を示してくれたのです。さて、その「道」とは?
登場人物の行動だけでなく、考え方の変化にも注目して読んでください。
児童書のおすすめ(12月10日)
書名 :はじめて読むレオナルド・ダ・ヴィンチ
著者 :石崎 洋司/著
講談社
--------------------------------------------------------------------
レオナルド・ダ・ヴィンチといえば、「モナリザ」や「最後の晩餐」で知られる有名な芸術家です。しかし、彼がどんな人だったのか、みなさんは知っていますか。
レオナルドは、裕福だけど複雑な家庭で育ちました。そして、モデルになれるほどの美少年だったのです。
画家としてよりも先に、楽器を弾きながら即興で歌う音楽家として有名になりました。ほかにも、科学者であり技術者でもあったことはよく知られていますが、幾何学、物理学、解剖学とあらゆる分野で才能を発揮しました。飛行装置や、人体の解剖図を見たことがあるという人も多いでしょう。まさに天才といえる人でした。
そんな天才でも、うまくいかない時期もありましたが、自分の信念を曲げず、理想を追求していくことがレオナルドのいちばんの才能だったのかもしれません。
ルネサンスという激動の時代の中で、文化や科学の最先端を走っていたレオナルド。彼について調べてみませんか。
児童書のおすすめ(12月3日)
書名 :神社・お寺のふしぎ100
著者 :田中ひろみ/文 藤本頼生/監修
偕成社
--------------------------------------------------------------------
いよいよ師走になり、今年もあと1箇月をなりました。年が明けてお正月は、親戚と集まったり、お年玉をもらえたり楽しいことがたくさんですよね。
ところで皆さんは、初詣に行ったことはありますか?初詣で神社やお寺に行くのが楽しみという人も多いと思いますが、神社やお寺は普段の生活の空間とは違って、大きな鳥居があったり、お参りの時に線香をあげる場所があったり、不思議なことがたくさんあると思います。
この本では、神社やお寺の不思議について、Q&A形式で100個紹介されています。「お賽銭の金額はいくらがいいの?」や「おみくじは、家に持ち帰ってもいいの?」など、初詣ですぐに役立つものから、「神様や仏様は、どこからきたの?」のような深いお話まで、いろいろなおはなしが載っています。
ぜひ、この機会に神社やお寺の不思議にふれてみてください。
児童書おすすめ(11月26日)
書名 :こどもに聞かせる一日一話 「母の友」特選童話集
著者 :福音館書店「母の友」編集部/編
福音館書店
--------------------------------------------------------------------
「子どもも大人も一緒にお話の世界へ遊びにいきましょう」という言葉で始まるこの本には、雑誌「母の友」で長く続く企画「こどもに聞かせる一日一話」の中から選ばれたお話を中心に、みんなが大好きな絵本の人気者「ぐりとぐら」や「だるまちゃん」が登場するお話などが30話掲載されています。
「ねぇ何かお話してよ」と子どもにお願いされたら、この本のお話を一日一話読んであげてみて下さい。「今日はどのお話にする?」と一緒に選んだり、お気に入りのお話が見つかれば繰り返し読むこともできます。寝る前に読んでもらえば、幸せな夢の世界へ飛び立つこともできるのです。
子どもはお話を読んでくれた人のことを、忘れることはないといいます。自分だけに向けられたあたたかなまなざしと声は、大人になってもお話とともに心に残り続けるのです。この本との出会いが、子どもと大人が心をかよわせるきっかけになることを願っています。
児童書のおすすめ(11月19日)
書名 :絵画をみる、絵画をなおす保存修復の世界
著者 :田口 かおり/著
偕成社
--------------------------------------------------------------------
みなさんは、世界で一番古い絵画を知っていますか?現存する世界最古の絵画は、4万年以上前に描かれた洞窟壁画といわれています。何万年何百年という途方もない年月を経てなお現代の私たちが美術品を鑑賞できるのは、さまざまな人々の手によって大切に受け継がれてきたからです。
美術品に携わる職業に“修復家” という仕事があります。修復家とは、その名のとおり作品をなおす専門の職人のことです。
「修復家の仕事はじっくり観察することからはじまる」と著者の田口かおりさんは語ります。作品の歴史をたどり、その作品にとって最もふさわしい修復方法を選び、後世へと伝えていきます。修復家は、過去・現在・未来を繋ぐ大切な役割を担っているのです。
美術館などで鑑賞する際は、修復家をはじめとした美術品に携わってきた人々にも思いを巡らせてみてください。
児童書のおすすめ(11月12日)
書名 :漢字びっくり事典
著者 :こざき ゆう/文 金田一 秀穂/監修 加納 徳博/絵
ポプラ社
--------------------------------------------------------------------
私たちが、ひらがな・カタカナとともに使いこなしている漢字。今から約3500年前に生まれたといい、長い歴史を持っています。学校でも習う身近な存在の漢字ですが、まだまだ知らない世界がたくさんあります。
くさかんむり、しんにょう、もんがまえ…。漢字に習う時に覚えた部首。部首は、200種類以上もあるとされます。「けものへん」の「けもの」とは、何の動物が元になったか知っていますか?是非、本を手に取って確かめてみてくださいね。
漢字の成り立ちや歴史、なんて聞くとなんだか難しく感じてしまうかもしれませんが、後ろの章では、クイズ形式に沿って楽しく漢字に触れることができます。国や偉人、植物の名前。そうだったの!?と驚くものもあるかもしれません。イラストが添えられているので、もし漢字に苦手意識を持っていても、楽しく読み進められますよ。
児童書おすすめ(11月5日)
書名 :SDGsってなあに?みらいのためにみんなができること たべる
著者 :関 正雄/監修 WILLこども知育研究所/編・著
株式会社 金の星社
--------------------------------------------------------------------
みなさん、SDGsという言葉を聞いたことありますか。世界中のみんなで協力して解決していく問題のことです。目標は17個で世界中の人々が力を合わせて取り組み、2030年までに目標を達成することを目指しています。問題を解決するためには大きく社会を変える必要があります。そして、世界中のだれ一人取り残さずに達成することが大切です。
目標の一つに「飢餓をゼロに」がありますが、みなさんは、ごはんの食べ残しはないでしょうか。豊かな国では食べ物が捨てられている一方で、その日の食べるものにも困っている人たちがたくさんいます。食べられる量だけ買う、食べ残しはしないなど、むだになる食べ物をできるだけなくなす目標をもちましょう。
また、余った食料をあつめて、必要な場所へとどけるフードバンクという活動もありますので、利用してみてはどうでしょうか。
児童書のおすすめ(10月29日)
書名 :そらのことばが降ってくる 保健室の俳句会
著者 :髙柳 克弘/作
ポプラ社
--------------------------------------------------------------------
クラスになじめず保健室登校をしている中学二年生のソラは、同じように保健室に通うハセオから俳句の句会にさそわれます。ソラはのらりくらりとそのさそいをかわしますが、ハセオが俳句を作る姿を見て段々と興味がわいてきます。
そしてソラ、ハセオ、養護の先生の三人で初めての句会を行います。そこでハセオが作った俳句がソラを深く傷つけてしまいました。
しかし、ハセオがソラに向けて詠んだ俳句は、決してソラを傷つけるための俳句ではありませんでした。ハセオが俳句に込めた本当の気持ちはソラに伝わるのでしょうか。
自分の気持ちを言葉にして相手に伝えることの難しさ、その言葉を理解してもらえたときの喜び、言葉が持つ人を元気にする力を教えてくれる物語です。
児童書のおすすめ(10月22日)
書名 :おとな体験授業?
著者 :なかがわ ちひろ/作
アリス館
--------------------------------------------------------------------
今日の授業は「おとな体験授業」。
5人の生徒たちはグループになって、自分がどんなおとなになりたいかをそれぞれ紙に書きます。
不思議なランプに火をつけ、ビーカーの中の金色の液体に紙を入れると、もわもわとした湯気がひろがり、おとな体験の世界へ出発です。
けれども、自分がなりたい仕事を体験できるのかと思っていたら、友達がなりたいと言っていた仕事を体験することになってしまい…。
自分がなりたい仕事ではなくてもそれが意外と得意なことだったり、将来の可能性が広がったりと、体験することで気づくことがあるということを教えてくれる一冊です。
どんな仕事をしたいのか、どんな大人になりたいのか、今はまだわからないことが多いと思いますが、これからいろいろな体験をすることで、将来本当になりたい自分を見つけることができるのかもしれませんね。
児童書のおすすめ(10月8日)
書名 :ぼくは本のお医者さん
著者 :深山 さくら/作
佼成出版社
--------------------------------------------------------------------
小さなころから大好きだった絵本や読み物、図鑑など、何回も読んで破れ、痛んでしまってもずっと手元に置きたいと思うことはありませんか?
そんな思いに応えてくれる人がいます。
製本会社を営んでいる齊藤英世さんは、本業のかたわら本の修理をする「ブックスドクター」の仕事も行なっています。
本の修理とは新品のようにきれいしてお返しすること?いえいえ、そうではありません。一冊一冊の本には持ち主の本に対する思い出、歴史があります。手あかや小さな汚れ、それらを残しながら元の雰囲気を壊さないよう最小限の修理を施していきます。
本にはデジタル化の波が押し寄せていますが紙の手触り、インクの匂い、ページをめくる音、五感で感じられる実物の本も人々の思いによって残されていくのかもしれません。
昔、読んだ本を取り出してそっとなでてみたくなる1冊です。
児童書のおすすめ(10月1日)
書名 :なんで勉強しなきゃいけないの? 1
著者 :W I L Lこども知育研究所/編著
金の星社
--------------------------------------------------------------------
あなたは学校の勉強が好きですか?宿題なんてやりたくないですか?
この本は5人の著名人がそれぞれ、子どもの頃はどんな子どもだったのかを思い返し、大人になった今、どうして勉強をした方がいいのか、自分の考えを語っています。その著名人のひとりで紛争解決請負人の伊勢﨑賢治さんは世界で生き抜くためには国際感覚が必要だと言っています。その国際感覚とは「さまざまな国の価値観を知り、その国に対して尊敬の心をもつこと」「相手と話し合うとき、ひきょうなまねをしないこと」「言いたいことをはっきり言うこと」を基本にしています。この考え方は、国に対してだけでなく、個人対個人のコミュニケーション時にも大事なことではないでしょうか。
ひとえに勉強というと難しく考えてしまいがちですが、いろいろな人の考え方を知り、こんな考え方もあるのかなと共感できたら、あなたの勉強に対する立ち位置が今よりもっと楽しいものになるかもしれません。
児童書のおすすめ(9月24日)
書名 :最後の語り部
著者 :ドナ・バーバ・ヒグエラ/著 杉田七重/訳
東京創元社
--------------------------------------------------------------------
彗星が地球に衝突するとわかり、一部の選ばれた人々は、別の惑星を目指して旅立つことになりました。主人公のペトラも選ばれたひとりです。そのころ地球では、多様性を否定し、コレクティブという単一社会をつくる、という運動が広がっていました。
ペトラはいつもお話を語ってくれた祖母を残し、自分の目がほかの人とは違う見え方であることを秘密にして、宇宙船に乗り込みます。眠っている間に目的地へ着く予定でしたが、381年経って目覚めたとき、コレクティブの人々が船内を支配していました。地球から来たペトラ以外の人たちは、眠っている間に記憶を消され、従わない者は排除されていたのです。
ペトラは自分に地球の記憶が残っていることを気づかれないよう注意しながら、コレクティブ社会からの脱出を計画します。それを支えてくれたのが、祖母が語ってくれたお話でした。
受け継がれるお話の力強さを感じることができる、読み応えのある物語です。
児童書のおすすめ(9月17日)
書名 :給食が教えてくれたこと
著者 :松丸 奨/著
くもん出版
--------------------------------------------------------------------
私が給食で思い出すのは、毎月1回の「お楽しみ給食」。各クラス順番に好きなメニューをリクエストできたのです。でもみんな好きなメニューは似たり寄ったりで、ココアパンやゼリーなど、とにかく定番の人気メニューがよく登場していました。
さて、この本の著者の松丸さんは、給食の献立を考える栄養士さん。実は給食が大嫌いだったそうです。野菜も魚もお肉も嫌い! 苦手な食べ物が多すぎて、給食はほとんど食べられませんでした。そんな松丸さんに、栄養士さんがこう話してくれます。
「全部が無理なら、一口でも食べてみて。きっといいことが起こるよ。」
それからというもの、鉄棒の逆上がりができたり、テストでいい点がとれたり、背が伸びたり、風邪をひかなかったり、いいことは何でも給食のおかげだと思うようになりました。松丸さんが栄養士を目指したきっかけです。
栄養士の仕事のこと、それから皆さんに伝えたいこと。ぜひ手に取ってみてください。
児童書のおすすめ(9月10日)
書名 :長い長い夜
著者 :ルリ/作・絵 カン・バンファ/訳
小学館
--------------------------------------------------------------------
この物語は名前のないペンギンの「ぼく」と、その「父さん」たちのお話です。
最初に登場するのはシロサイのノードン。彼は理不尽な人間によって大切な家族や仲間を奪われてしまいます。それからの彼にとって、悪夢を見そうで眠れそうにない日は、夜がいっそう長くなるのでした。
ある日、ノードンは1匹のペンギン、チクと出会います。チクも人間同士の戦争によって、大切な仲間を失いますが、なんとか守ることのできた卵を運んでいました。2匹は戦争で火事になった動物園から逃げ出し、暗い悲しい気持ちの中、卵を守るため旅に出ます。
この旅の中で彼らは、家族や仲間との大切な想い出を語り合いながら、お互いを支え合っていきます。
そして、語り継がれた沢山の思い出は、卵だった「ぼく」を励まし、生きていく勇気をくれました。
私たち自身も、色んな出来事やたくさんの出会いがあって、今の自分がいるということに気づかせてくれるお話です。
児童書のおすすめ(9月3日)
書名 :コーリング・ユ-
著者 :永原 皓/文
集英社
--------------------------------------------------------------------
元気で賢いシャチの男の子「カイ」がこの物語の主人公。カイは好奇心旺盛な為、お金目的でシャチを捕獲していた漁師に捕まってしまいます。カイを心配した仲良しの従妹の「エル」は、わざと網に入りカイと一緒に捕まってしまうほどカイのことが大好きでした・・・・。人間の身勝手さにより家族から引き離されてしまったカイは、その魅力で、一つ一つ困難を克服していきます。
異種別であっても他者を思いやることのできる優しさや、苦境に立たされても決して希望を失わないカイの強さは、読者に真の勇気とは何かを鮮やかに印象づけ、又、対照的に彼の行動から、私利私欲の為に他者を傷つけても平気な人間の愚かさも浮き彫りになります。
地球に生きる全ての仲間が共存していること、その為に大切なことは何かを教え気付かせてくれる一冊です。読後は、カイに魅了されること間違いなしの、【第34回小説すばる新人賞】を受賞した作品です。
児童書のおすすめ(8月27日)
書名 :車いすでジャンプ!
著者 :モニカ・ロー/作 中井 はるの/訳
小学館
--------------------------------------------------------------------
エミーは車いすモトクロスにあこがれる13歳の女の子。生まれた時から脊椎に障がいがあります。モトクロス用の高性能な車いすを買うため、友だちのアレエとオンラインショップを運営しています。売り上げも上々で夢に向かって進んでいたのですが…
エミーは車いすで過ごせるところでは、何でも自分でできます。でも、それをわかってくれない人がたくさんいます。
ある日、学校からエミーの車いすを買う資金集めをするという手紙が届きます。エミーはうれしくて、何かがひっかかっていることに気づかないふりをしていました。それがこんなに大事になるとは思いもしないで。
障がいを持つ人にとって必要なこととそうでないことは、周りの人が思うそれとは違うのかもしれません。お互いがちゃんとコミュニケーションをとることが大切です。決めつけではなく、当事者の声をよく聞いて行動することが大事だと教えてくれる1冊です。
児童書のおすすめ(8月20日)
書名 :みんなの少年探偵団
著者 :万城目 学、湊 かなえ、小路 幸也、向井 湘吾、藤谷 治/著
ポプラ社
--------------------------------------------------------------------
明智小五郎に怪人二十面相。江戸川乱歩作品が好きな人は、その名を聞いたことありますよね。
『怪人二十面相』や『少年探偵団』の生みの親で、日本探偵小説の父と称される江戸川乱歩の生誕120年を記念して発刊されたこの本は、万城目学や湊かなえといった現代の著名な作家たちが、作品の世界観をそのままに、新たな物語を紡いだ短編集です。
物語の第1編では、早くに両親を失い、父方のおじいさんと暮らすこととなった双子の少年が、それぞれの特別な能力を駆使しながら、おじいさんが関わった事件の謎を解いていきます。はたして二人の運命は?ラストには読者を驚かせる展開も。何度も読み返したくなる作品です。
今年は江戸川乱歩の生誕130年、乱歩の世界に浸る絶好の機会です。
学校の図書室で手に取ったことのある方も、初めて触れる方も、江戸川乱歩の魅力を再発見できる、懐かしさと新鮮さを兼ね備えたこの短編集をぜひ、手に取ってみてください。
児童書のおすすめ(8月13日)
書名 :『オニのサラリーマン じごくの盆やすみ』
著者 :富安 陽子/文 大島 妙子/絵
福音館書店
--------------------------------------------------------------------
盆やすみ、みなさんは何をしますか?夏休みの人もいれば学校や仕事などの人もいますよね。
この絵本の世界は、じごく。じごくカンパニーで、はたらくオニのサラリーマンはお盆も仕事のようです。それもそのはず、日々じごくにいる「もうじゃ」たちはお盆なので里帰り!その間にオニたちはねんにいちどのおおそうじです。
「せいりせいとん」「あけたらしめよう」といったこのよの学校や職場にもあるような注意書きやじごくのいろんな場所ではたらくオニたちが登場します。
オニがサラリーマンというせっていもおもしろいですいね。
盆やすみにご先祖様のことを考えたり、昔飼っていたペットのことを考えたりしながら、読んでみてください。
児童書のおすすめ(8月6日)
書名 :『チームでつかんだ栄光のメダル 陸上男子400mリレー 山縣・飯塚・桐生・ケンブリッジ』
著者 :本郷陽二/著
汐文社
--------------------------------------------------------------------
今年はパリでオリンピック・パラリンピックが開催されています。この4年に1度の大舞台に出るため、血のにじむような努力を重ねてきた世界各国のスーパーアスリートが集まります。さまざまな種目で日本選手の活躍もとても楽しみですね。
オリンピックでの陸上競技短距離種目では、日本選手個人でのメダル獲得はまだありませんが、リレー競技では4×100mリレーで過去に男子チームが2度(2008年の北京オリンピック、2016年のリオオリンピック)メダルを取っています。
日本選手は個人種目の100mでは、1932年のロサンゼルスオリンピック以来、決勝進出さえできていないのに、リレーではメダルが取れるなんて驚きですよね。
この本には数字のうえでは勝ち目がなかった日本チームが、リオオリンピックでメダルをつかむまでの知られざる物語が記されています。
ぜひ、観戦とあわせて読んでみてください。
児童書おすすめ(7月30日)
書名 :『プーさんと出会った日』
著者 :リンジー・マティック/作 ソフィ-・ブラッコ-ル/絵
評論社
--------------------------------------------------------------------
プーさんが本当に実在したクマさんだったことを、ご存じですか?この絵本は、世界中のクマさんの中で、一番有名なプーさんのモデルとなったクマさんの本当にあった半生を描いたお話です。
獣医師のハリ-・コ-ルボ-ンは、戦争に向かう途中の駅で子グマと出会います。彼は「このクマには、何か特別なものを感じる」と子グマを戦場へ連れていくことに悩みながら引き取ります。ハリ-は、誰よりも温かい心の持ち主の獣医師でした。クマさんは、ハリ-の故郷にちなみ“ウィニペグ”と名付けられ、ハリ-の良きパートナ-となりました。賢いウィニペグは、隊員達の心を癒し、部隊のマスコットとして大事にされていました。しかし、戦況が悪化し、ハリ-はあることを決断しなければなりませんでした。でも、そこからまた、ウィニー(ウィニペグ)の新しい第2章が始まります。
ハリ-がウィ二-に「何か特別なもの」を感じたように、この本を読んだあなたもきっと、ウィニーに「何か特別なものを感じる」のではないでしょうか。
児童書おすすめ(7月23日)
書名 :『こちらゆかいな窓ふき会社』
著者 :清水 達也/訳 清水 奈緒子/訳 クェンティン・ブレイク/絵
評論社
--------------------------------------------------------------------
子どもの頃、一番好きな児童文学の作家はロアルド・ダールでした。ブラックユーモアがピリリときいた奇想天外なストーリーと、クェンティン・ブレイクが描く味のある挿絵に、小学生の私は夢中になって読んでいました。どれも思い入れがあるものばかりですが、ダールの作品を初めて読む人には、この『こちらゆかいな窓ふき会社』をおすすめします。
ビリーの家の近くにあるオンボロ空き家が、ある日、<はしご不要窓ふき会社>になりました。中から顔を出したのはなんと、キリンとサルとペリカンだったのです。さて、このへんてこりんな3人(3びき)組でどうやって窓ふきをするのでしょうか…?
最後にサルが歌う別れの歌は、仲良しの動物たちと別れるビリーへ、そして物語を読んでいる私たち読者へむけて、「本を開けばまた会える」というダールからのメッセージのようにも感じられます。お話が終わってしまうさみしさを優しく包み込んでくれる、私の大好きな場面です。
児童書おすすめ(7月9日)
書名 :『今日も嫌がらせ弁当 反抗期ムスメに向けたキャラ弁ママの逆襲』
著者 :ttkk/文
三才ブックス
--------------------------------------------------------------------
毎日のお弁当。作っている人はどんな気持ちなのでしょう。この本は、母を無視して返事をしない反抗期真っ盛りの高校生の娘とそんな娘へのささやかな抵抗として、ちょっと変わったキャラ弁を作り続けた母の3年間の記録です。
母は、仕事や家事で忙しくて疲れたときも、娘にウザがられても、キャラ弁を毎日作ります。「自分でオキロ」やもらったプレゼントへの「ありがとう」のメッセージなど、母の気持ちはお弁当の“のり文字”で伝えています。「普通のお弁当がいい」と言う娘ですが、残さず食べてきます。毎日お弁当を作っている母としては、空っぽになって返ってくるお弁当箱を見るのは嬉しいものです。
娘への嫌がらせで始めたキャラ弁ですが、このキャラ弁は、高校3年間を見守ってきた母から娘へのメッセージであり、無口な娘とのコミュニケーションツールになっていたようです。
あなたのお弁当にも「毎日健康に」「テストや部活を頑張って」など、作っている人の気持ちも一緒に詰められていると思います。
児童書おすすめ(7月2日)
書名 :『いただきます!からはじめるおさかな学』
著者 :鈴木 允/著 生駒 さちこ/イラスト
リトルモア出版社
--------------------------------------------------------------------
皆さんが普段食べている魚は、いったいどこから来たのか、知っていますか?
この本には、魚がとれて、値段がついて、お店に並ぶまでの流れから、日本の魚文化、海の環境問題など、魚に関するいろいろなことが分かりやすく説明されています。
自分が食べている魚が、どこで、どうやってとれたものかを知ると、普段の魚料理がいつもよりおいしく感じるかもしれません。魚のさばき方や身近な魚のQ&Aなども載っていて、魚を見るのも食べるのも楽しくなる一冊です。
身近な魚について知っていくと、魚が減っていることや、ごみの問題など、今起こっている海の環境問題がより身近な問題に感じてきませんか?
現在、日本でも取り組まれているSDGsの目標14の中に「魚のとりすぎをなくす。」という目標があります。
おいしい魚をずっと食べられるように、自分たちに何ができるか、この本を読んで考えてみませんか?
児童書おすすめ(6月25日)
書名 :『くらべて発見 食べものはどこからきたの?』
著者 :木本栄/訳 日本語版監修/藤原辰史
ほるぷ出版
--------------------------------------------------------------------
あなたが今日口にした食べものは、どのように作られているのでしょうか。これはドイツに住む作者が食べものを作っているところを訪れ、じっさいに見たり聞いたりしたことを描いた本です。
本を開くと右ページに大きな農園、左ページに小さな農園があり、大きなところと小さなところでの作業の違いがひと目でわかります。絵についている説明でさらに詳しく知ることができますよ。この本に出てくる食べものは牛乳、パン、魚、肉、りんご、卵、トマトの7種類です。とても身近な食べものですね。この本はドイツでのお話ですが、かなりの部分が日本の農業や畜産、漁業にも当てはまるそうです。もし近くに食べものを作っている方がいらっしゃったら、今度は自分でお話をきいてみるのもよいかもしれませんね。
児童書おすすめ(6月18日)
書名 :『江戸の空見師嵐太郎』
著者 :佐和みずえ/作 しまざきジョゼ/絵
フレーベル館
--------------------------------------------------------------------
江戸の下町に暮らす嵐太郎は、雲の流れや風の強さ、空気のしめりぐあいなどを観察し、天気を予想するのが得意な少年です。衣替えのタイミングや、頭痛もちの奥さんのごきげんうかがいなど、町の人からひっきりなしに相談がきては、ぴたりと天気を当てるので嵐太郎の評判は江戸中に広がっていきました。
ある日、嵐太郎のもとに、奉行所から秘密のお役目が舞い込みます。それは空見の技で「黒船来航の日を予測せよ」というとんでもない仕事でした。
嵐太郎はどうやって黒船が来る日を予測するのでしょうか。
現代の気象予報は、人工衛星で宇宙から雲の動きを見たり、スーパーコンピュータで台風の動きをシミュレーションしたり、予測技術がとても進歩しています。
江戸時代の天気予報と現代の天気予報を比べてみるのも面白いですね。
児童書おすすめ(6月11日)
書名 :『じぶんでできた!』
著者 :杉崎 聡美/著 竹下 和男/監修
ほるぷ出版
--------------------------------------------------------------------
お弁当作りというと、早起きして、料理して、弁当箱に詰めて……なんとなく「大変そう」なんて思っていませんか。
これから先、一人でお弁当を作らなければならない時がくるかもしれません。何から始めていいか分からない、そんなあなたも安心。弁当箱の選び方から後片づけの仕方まで、漫画を交えて楽しく学ぶことができます。
巻末には初級・中級・上級の「お弁当レシピ」が紹介されていて、初級はスーパーやコンビニのお惣菜を使ったお弁当作りから!
お米の炊き方が分かったら「基本のおにぎり」など、無理のないお弁当作りを始めることができますよ。
家族につくってもらったお弁当もおいしいけれど、自分で作ったお弁当は、もっともっと、おいしいかも!
児童書おすすめ(6月4日)
書名 :『雨の日が好きな人』
著者 :佐藤 まどか/著
講談社
--------------------------------------------------------------------
小学6年生の七海は、お母さんが再婚して、新しいお父さんと2歳年上のお姉ちゃんができます。お姉ちゃんは病気で入院しているので、七海はまだ会ったことがありません。
家族が増えて喜んでいる七海でしたが、お母さんたちは、入院中のお姉ちゃんの心配ばかり。七海は1人でいることが前より多くなり、家族が増えたのではなく、お母さんを奪われたような気持ちになります。
複雑な家庭環境の中で、親友との関係もギクシャクしていき、七海は学校をズル休みするようになります。そして、七海は両親に内緒で、まだ会ったことがないお姉ちゃんに会いに病院に行きますが…。
七海は、病気のお姉ちゃんに嫉妬したり、きれいな友達と自分を比べて落ち込んだり、悩みながらも相手と向き合い、自分の本音を伝えて成長していきます。
雨の日が好きな人もいるし、嫌いな人もいます。自分と誰かを比べて悩んでいる人にぜひ読んでもらいた1冊です。
児童書おすすめ(5月28日)
書名 :『目で見ることばで話をさせて』
著者 :アン・クレア・レゾット/作
岩波書店
--------------------------------------------------------------------
19世紀初頭、マーサズ・ヴィンヤード島では、耳が聞こえる人も聞こえない人も手話で会話していました。家事よりも物語をつくるのが好きなメアリーも、手で多くのことを語ります。ところが、その語りをよろこんでくれた兄が馬車の事故で亡くなってからは、なぜ不公平なことがあたりまえなのか、どうしようもないことが起こるのか、疑問に思うようになりました。
そんなとき、島に科学者がやってきます。島に耳が聞こえない人が多い原因を調べに来たというのです。この科学者の言動にメアリーは度々苦しめられました。そんなメアリーに違う視点を示してくれたのが、奴隷から自由黒人となり、父の牧場で働いているトーマスです。科学者に誘拐され、差別を受けながらも、あきらめなかったメアリー。悩みながらも自分で考え、会話する努力をします。メアリーの疑問への答えは、会話の中にあるかもしれません。ぜひ手話での会話表現にも注目して読んでください。
児童書おすすめ(5月21日)
書名 :『ウィリアムの子ねこ』
著者 :マージョリー・フラック/作・絵 まさき るりこ/訳
徳間書店
--------------------------------------------------------------------
五月のある月曜日の朝、迷子の子ねこが町の通りを歩いていました。しかし、忙しい大人たちは誰一人子ねこに気がつきません。そんな中、子ねこに気がついたのはウィリアムだけでした。なぜなら、彼はまだ4才なのでちっとも忙しくなんかなかったからです。
『かわいい子ねこちゃん、きみ、どこからきたの?』とウィリアムが尋ねますが、子ねこは『ミュー、ミュー、ミュー』と鳴くばかり。そこで、ウィリアムは迷子の子ねこを警察に届け出ることにしました。ところが、飼い主だと名乗る人物が三人も現れて…。
果たして、子ねこは無事に飼い主の元へ帰ることができるのでしょうか?
少年の親切がまわりの人々を幸せにし、その親切がめぐりめぐって少年に返ってきて、最後には少年も含めすべての人が幸せになるおはなしです。みなさんも少しでも困っている人がいたら、勇気を出して手をさしのべてみませんか?
児童書おすすめ(5月14日)
書名 :『かぼちゃ人類学入門』
著者 : 川原田 徹/さく
福音館書店
--------------------------------------------------------------------
佐賀のおとなり、福岡の門司港から連絡船に乗って夢時間。海に浮かぶ大きなかぼちゃが見えてきたら、それは「かぼちゃ島」です。この島に住む人たちは、かぼちゃを食べ、かぼちゃの恵みに感謝しながらのんびり楽しく暮らしています。
島には、宿に温泉、市場や学校など、暮らしに必要なものは何でもありますが、皆さんの町にあるものとは少し違っています。例えば、この島の銀行ではお金だけではなく、健康や幸せも預けられます。そして、健康に恵まれなければ健康を、悲しい時には幸せを引き出すことができます。健康と幸せとお金は、1:2:10の割合で取引され、お互いにないものを補いあっています。
「世の中で一番広いものはなあに?」かぼちゃ人は、心の中だと語ります。かぼちゃ島は狭いけれど、空想をめぐらせば世界が無限に広がると知っているのです。
この本を開いてみてください。皆さんもかぼちゃ人として夢のような時間を過ごせるかもしれません。
児童書おすすめ(5月7日)
書名 :『日本の昔話 全5巻』
著者 : おざわ としお/再話、赤羽 末吉/画
福音館書店
--------------------------------------------------------------------
「むかし あるところに」で始まる昔話。「はなさかじい」や「ももたろう」、みなさんはどんな昔話を知っていますか?
昔話は日本各地で何百年にもわたり親から子へ、子から孫へと口伝えで語り継がれてきたおとぎ話です。昔話には、人が生きていくための知恵や教えがたくさんあります。
この「日本の昔話」全5巻では、今では直接聞くことができなくなった語り継がれた昔話301話が、子どもにもわかりやすい言葉で書き直され収められています。
初夢をみて宝物を手に入れる話、いつもいじめられていた子どもが活躍する話、正直者がご褒美をもらう話、猫やネズミが人間の知らない秘密を教えてくれるお話などなど。
ひとつのお話は短いので、ちょっとした時間にも読むことができます。知っているお話や、思いもよらない結末のお話もあるかもしれません。何回読んでも面白くて新しい発見がある、それが昔話の魅力です。
児童書おすすめ(4月30日)
書名 :『すごいゴミのはなし ゴミ清掃員、10年間やってみた。』
著者 : 滝沢 秀一/文、スケラッコ/イラスト、萩原 まお/イラスト
学研プラス
--------------------------------------------------------------------
皆さんは世の中にあふれる「ゴミ」が、どのように処理され、そして地球環境にどう影響するのか考えたことがありますか。この本は、10年間ゴミ清掃員として働いた著者の経験を通じて、ゴミの分別やリサイクル、清掃作業の役割、そしてゴミが抱える問題について教えてくれます。
「ゴミとは人の心だ」とこの本の著者は語ります。世の中にゴミとして生まれてきたものは一つもないはずなのに、私たちの暮らしを豊かにするために生まれてきた「モノ」は、きれいだから、汚いからではなく、その人がいらないと思った瞬間「ゴミ」になってしまうのです。ゴミは年々増え続け、環境省のHPには、約20年で日本のゴミ最終処分場が満杯になると記載されています。
「地球の未来を守るために何ができるのか」一緒に考えてみませんか。この本を読めば、皆さんが暮らす場所を、いつもきれいに保ってくれている存在に出会えるはずです。
児童書おすすめ(4月23日)
書名 :『朝ごはんは、お日さまの光!』
著者 : マイケル・ホランド/文
徳間書店
--------------------------------------------------------------------
やさしい手ざわりのこの本は、植物からできています。インクも植物からできています。
カラフルな絵と楽しい解説で、植物たちの知識を図鑑にも負けないくらいに幅広く教えてくれる、科学絵本を読んでみませんか?
さて、植物のごはんは何でしょうか?それは太陽の光です。では太陽のエネルギーが地球に届くまでの時間は?太陽の光を食べた植物が今度はわたしのごはんになるの?一つの謎の答えがまた謎を呼び、ページをめくるたびに、あなたはますます植物の不思議に引き込まれていくことでしょう。植物を使った楽しい遊びや実験も紹介されています。
植物がなければ、どんな生き物も生きていくことはできません。植物を知れば、すばらしい生命やモノのつながりが見えてきます。
児童書おすすめ(4月16日)
書名 :『ノクツドウライオウ』
著者 : 佐藤 まどか/著
あすなろ書房
--------------------------------------------------------------------
ノクツドウライオウ。何を意味することばでしょう? 答えは表紙に描かれた看板を見て解決です。
ノ靴
堂来往
右から読めば、そう、靴ノ往来堂。
横書きの文字を右から書くのは変に思うかもしれませんが、日本では1950年頃まで右から書くことは何もおかしいことではありませんでした。新聞の見出しも右から書かれた時期があります。調べてみると1952年に公用文は左から書くように通達され、それから現在のように左から書く体裁が定着したそうですよ。
さて、往来堂ですが、右から書かれた看板ということはずいぶん昔から営業しているのかしら。そうです、往来堂は100年続く老舗の靴屋。主人公の夏希は中学生で、代々続くこの店を継ぐか悩むようになります。別の夢があるけれど本来継ぐ予定だった兄が突然出て行ってしまったからです。
往来堂で起こる心温まる魔法のような出来事に、果たして夏希はどうなっていくのでしょう?おたのしみに。
児童書おすすめ(4月9日)
書名 :『出世できない孔子と、悩める十人の弟子たち。』
著者 : 下村 湖人/原作 森 久人/小説
Gakken
--------------------------------------------------------------------
この本は郷土の作家・下村湖人の『論語物語』を原作として書かれています。みなさんは『論語』って知っていますか。孔子という中国の昔の偉い人が、自分や弟子たちの言葉や行動をまとめたものです。それを物語にした『論語物語』を、子ども達でも読みやすい小説にしています。
優秀だけど高い理想を抱いて、世渡りに不器用な孔子と、孔子の元で学ぶ若い弟子たちが、一人ひとり個性的に描かれています。たくさんのエピソードから、彼らにも私たちと同じような悩みがあったことがわかって、2500年も前のこととは思えないくらい、親しみを感じてしまいます。
『論語』というと難しいものと考えがちですが、この本の中で孔子が悩める弟子たちに語りかける言葉は、まさに『論語』の世界です。日本でも古くから学ばれ、多くの人に影響を与えてきました。
子どもたちだけではなく、大人のみなさんにもぜひ読んでいただきたい一冊です。
児童書おすすめ(4月2日)
書名 :『13歳からの「手帳活用術」』
著者 : 小澤 淳/監修
メイツユニバーサルコンテンツ
--------------------------------------------------------------------
成功していると言われる人には、時間の使い方や優先順位のつけ方の上手な人が多い。
これを中・高生がしてみると、夢や目標に近づけると思うよ。そんなとき手帳は、願いを叶えるアイテムになる。
部活や塾で忙しいと思ったら、優先順位をつけて「今すぐする事」「〇日までにする事」と考えると自由に使える時間もできるよ。手帳を使うと、1日をどう過ごしたのかが見えてくる。「やるべき事リスト」を作ると、し忘れる事がなくなるから、「しなさい!」って言われることもなくなるね。
計画的な行動で時間の感覚を身につけたら、次は小さな目標をクリアするようにしよう。できたら「ゲームをする」等ごほうびとセットにして考えるといいよ。夢や目標の記入例やスマホの活用法も参考になると思う。
4月始まりの手帳もある。手帳は「なりたい自分」に近づくための強い味方になってくれるからね。
児童書おすすめ(3月26日)
書名 :『論理的思考力が育つ10歳からのおもしろ!フェルミ推定』
著者 : 横山 明日希/著
くもん出版
--------------------------------------------------------------------
「トイレの花子さんは日本に何人いるでしょう?」と聞かれたら、どうやって調べて、なんと答えますか?
他にも、「日本の学校にあるトイレットペーパーを全部つなげたら何メートルですか?」とか「日本の小学生の何人がスマホでゲームをしていますか?」と聞かれたらどうしますか?
インターネットで検索したら出てくるでしょうか?もちろん出てきません。算数みたいに公式に当てはめて正解を出す、ということもできません。
そんな、「正解が無い問題」について考える方法が「フェルミ推定」です。「推定」とは「ある事実をもとに、判断する」ことです。また、「答え」ではなく、「答え方」を考えます。
では、トイレの花子さん、トイレットペーパー、スマホでゲームする小学生の数を考えるための事実とは何でしょうか?そしてその事実を基にどう考えていくのでしょうか?
現代社会は、正解が無い問題であふれています。この本は、様々な問題について「自分で考えて、自分の答えを出すこと。そして分からないからといってあきらめずに挑戦すること」を学ぶための一冊です。
児童書おすすめ(3月19日)
書名 :『みぢかな樹木のえほん』
著者 :国土緑化推進機構/編 平田 美紗子/絵
ポプラ社
--------------------------------------------------------------------
学校の机の天板は何の木材から作られているでしょうか。答えは、ブナ材など。ほどよい堅さがあり加工もしやすいブナ材は、家具や食器など、さまざまな用途に利用されています。 日本は国土の約7割が森林におおわれており、私たちの暮らしは樹木と密接に関わっています。この本では多くの樹木のなかでも、特に身近な30種が、イラストと共に紹介されています。 樹木との関わりは人間だけのものではありません。葉や実を食べる虫、木の幹を巣として利用する鳥など、たくさんの生き物が樹木と共に生活しています。 さて、学校や公園には何の樹木が植えられて、どんな生き物が近くにいるでしょうか。あなたが使っている鉛筆やお箸は何の木材から作られているのでしょうか。 樹木と生き物、そして私たちとの関係を知り、考えることで、今までとは違う景色が見えてくるはずです。
児童書おすすめ(3月12日)
書名 :『きみは「3.11」をしっていますか?』
著者 :細野 不二彦/まんが 平塚 真一郎/ノンフィクション 井出明/まとめ
河北新報社/特別協力 小学館
--------------------------------------------------------------------
2011年3月11日に起きた「東日本大震災」から今年で13年。巨大な海洋プレートがはじけ、大きな津波が太平洋沿岸部を襲いました。2024年1月1日には「能登半島地震」が発生し、津波や地震に伴う火災により多くの命や日常生活が失われました。被災地では現在も復旧・復興が進められています。
日本は災害がとても多い国です。歴史をふりかえると、昔から数多くの災害に見舞われ、自然の恐ろしさを体験してきたことが分かります。この本の第3章には、東北を代表する新聞社「河北新報社」が集めた、41人の被災地の「声」が紹介されています。観測史上最大規模の災害だった東日本大震災に対して、人々はその困難と悲しみをどのように乗り越えてきたのでしょうか。
天災は忘れたころにやってきます。ぜひ、この本を「遠い誰か」の出来事ではなく、「自分のこと」として読んでみてください。
児童書おすすめ(3月5日)
書名 :『サンゴの海』
著者 :長島 敏春/写真・文
偕成社出版
--------------------------------------------------------------------
3月5日は3(さん)5(ご)という語呂合わせと、サンゴの石が3月の誕生石でもあることから、サンゴの日という記念日になっています。海の写真や映像で、よく見かけるサンゴですが、皆さんは、サンゴについてどのくらい知っていますか?
実は、サンゴ礁はきれいなだけではなく、地球や人間にとって大切な働きをしてくれています。
この本は、石垣島のサンゴと海の写真を使って作られた美しい写真絵本です。長年石垣島の海を取り続けている写真家、長島敏春さんの写真は眺めるだけでも目を楽しませてくれます。
写真だけでなく、サンゴの種類や生態、サンゴと共生する生き物たちをわかりやすく知ることができ、サンゴについて知るきっかけになる一冊です。
地球温暖化や環境の変化によってサンゴが減っていることにも触れており、環境問題についても考えるきっかけになります。今日は美しい海の写真を見ながら、海の環境問題について考えてみるのはいかがでしょうか?
児童書おすすめ(2月27日)
書名 :『父は空 母は大地』
著者 :寮 美千子/作
ロクリン社
--------------------------------------------------------------------
1854年、アメリカのピアス大統領が、インディアンたちの土地を買収したいと申し出ました。この本は、その時、先住民インディアンの首長シアトルが、大統領に宛てた手紙を絵本にしたものです。「大統領が土地を買いたいと言ってきた。どうしたら空や大地を買えるだろう」と言った言葉は、美しい大地や自然を理解し、大切に思っている事が伝わってくる印象的な一文です。 木々は伐採され、水、空気は汚れ、地球は沸騰化し壊れかかって生き物は住めなくなってしまうかもしれません。シアトル首長や、インディアンたちは、こうなることを知っていて教えてくれていたのに、なぜ私たちも気付いていたはずなのに一人一人が行動を起こさないのでしょうか?紛争・宗教・自然環境破壊・多様な生物との共存などの問題に直面している今だからこそぜひ読んでほしい1冊です。
児童書おすすめ(2月20日)
書名 :『大おばさんの不思議なレシピ』
著者 :柏葉 幸子/作 児島 なおみ/絵
偕成社
--------------------------------------------------------------------
中学一年生の美奈は、家庭科が大の苦手。ほうちょうを持てば手を切る。ミシンは美奈がやるときだけ糸がからまる。塩味のホットケーキが焼きあがったり、さとう入りのスープがにえたぎったりする。 そんな美奈が家の納戸から見つけたのは、大おばさんの一冊の古いレシピノートでした。縫い物から編み物、料理、家庭薬の作り方まで、さし絵入りでていねいにのっています。しかし、ノートにのっている名前は『星くず袋』に『魔女のパック』、『竜のよだれかけ』、『魔術師の七面鳥』など見たことも聞いたこともないものばかり。 このレシピ通りに作りはじめると、たまに美奈は不思議な世界に行けるように…。そこには美奈がつくったものを必要としている人たちが待っていました。美奈のつくったものが、思わぬ方法でその世界の難題解決に一役買うことになります。読むと自分も何か手作りをしてみたくなる物語です。
児童書おすすめ(2月6日)
書名 :『月夜のチャトラパトラ』
著者 :新藤 悦子/著
出版社 :講談社
--------------------------------------------------------------------
洞窟ホテルを営む家の子どもカヤは、チャトラパトラと呼んでいる秘密の小さな友だちがいます。悪い人に見つからないように、チャトラパトラのことをカヤは誰にも話していませんでした。ところがある年の冬、吹雪の晩に洞窟ホテルを訪れた旅行者が、チャトラパトラを探しているとカヤは知ります。「大きい人には見えない」とチャトラパトラは言いますが…。
トルコのカッパドキア地方を知っていますか。無数の奇岩がそびえ立つ不思議な景観と、岩をくり抜いて作られた住居や教会などの岩窟群、さらには壮大な地下都市があることで有名な世界遺産で、熱気球の遊覧飛行や洞窟ホテルが人気の観光地です。観光シーズンは夏。冬は雪に覆われ何日も外に出られないこともあります。でも、雪化粧をした奇岩の風景や、暖かい洞窟ホテルでおいしいトルコ料理を食べてゆったり過ごすのは、冬にしか味わえません。そんな冬のカッパドキアへ旅した気分になれる、少し不思議なお話です。
児童書おすすめ(1月30日)
書名 :『香菜とななつの秘密』
著者 :福田 隆浩/著
出版社 :講談社
--------------------------------------------------------------------
みなさんは学校にある掲示板を見ていますか?校内にどんな植物があるか、知っていますか? 主人公の香菜は観察が得意。よく観察すると、いつだって新しい発見があり、ささやかな秘密がひそんでいるのです。 五年二組に転校生してきた広瀬くんにも、どうやら秘密があるようです。そんな広瀬くんの様子をうかがう香菜でしたが、読み聞かせ絵本を選ぶアドバイスをしたことがきっかけで、ふたりは話をするようになりました。香菜は話すことが苦手ですが、不思議なことに広瀬くんは、うまく伝えられないこともわかってくれるのです。広瀬くんと一緒に行方不明になった男の子を探したり、暗号の謎を解いたりすることで、香菜は考えるだけでなく、行動するようになります。そして、自分の考えを、みんなに伝えることができたのです。 謎解きだけでなく、観察すること、意見に耳を傾けること、伝えることについて考えながら読むと、あらたな発見があるかもしれませんよ。
児童書おすすめ(1月23日)
書名 :『星屑すぴりっと』
著者 :林 けんじろう/文
出版社 :講談社
--------------------------------------------------------------------
「映画が、みたい、のう」 イルキには、十歳以上も年の離れたいとこのせいちゃんがいます。せいちゃんは大学生の時に難病を患い、杖を使って歩くことさえも困難でした。イルキは、そんなせいちゃんのために、せいちゃんが観たかった映画を同級生のハジメと一緒に観に行きます。 映画が上映される場所は京都。中学生ふたりで急に旅行なんてできっこないと思っているイルキと、まずは検証だと言って旅行に行くことができると迷いがないハジメ。このように、正反対な考えを持っているふたりだからこそぶつかり合いがあり、笑いがあり、次へ次へとふたりの会話に引き込まれます。 ハジメにもこの旅に行く目的が秘かにありました。独特な大阪の方言で話すハジメにも注目してみてください。
「映画が、みたい、のう」 せいちゃんが観たかった映画をふたりは観ることができたのか。せいちゃんが、こぼしたこの言葉に込められた想いを想像しながらぜひ読んでみてください。