小中学生へおすすめ!
児童書のおすすめ(9月9日)

書名 : 捨てないパン屋の挑戦
著者 : 井出 留美/著
出版社 : あかね書房
日本では、1年間に400万トン以上の食品が廃棄されています。これは私たち一人ひとりが、おにぎりを毎日1個捨てていることになる量です。環境のことを考えても、食品ロスは大きな社会問題です。
パン屋に生まれた田村さんは、どうして捨てないパン屋になったのでしょうか。子どもの頃はパンが嫌いだった田村さん。しかし、実家のパン屋を継いでからは、フランスまでパンの修業に行くほどになりました。そして、まき窯で天然酵母を使ったパンのみを作るようになり、売れ残ったパンを捨てることがなくなったのです。材料や販売方法など試行錯誤の末に、やっと捨てないパン屋になることができました。それはとても長い道のりでしたが、必要な選択でした。
パン屋だけではなく飲食店や販売店、家庭からも日々食品が廃棄されています。これは、私たちみんなが向き合っていかなければならない問題です。食品ロスについて、考えるきっかけにしてほしい本です。
児童書のおすすめ(9月2日)

書名 : 子どもにウケる将棋超入門
著者 : 創元社編集部/編
出版社 : 創元社
皆さんは将棋にどんなイメージを持っていますか?多分、多くの人が難しそうだと思っているのではないでしょうか。
ですが、この本を読んだら、そのイメージも一気に無くなります。将棋を全く知らなくても、丁寧な解説付きなのですぐに将棋を楽しめます。
将棋は、全部で40枚の駒から成り立つゲ―ムです。そのうち、玉将と王将、飛車、角行、金将、銀将、桂馬、香車、歩兵と呼ばれる8種類の駒に分けられます。盤に並べた駒を2人で交互に動かし、相手の王さまの駒を取ると勝ち、取られたら負けです。
この本では、将棋の打ち方や対局の仕方、プロの棋士等について詳しく書かれています。練習ができる棋譜も付いていますので、何回でも楽しむことができます。
最初は、家族や友達と始めてみるとより面白いと思います。ぜひ、挑戦してみてください。
児童書のおすすめ(8月26日)
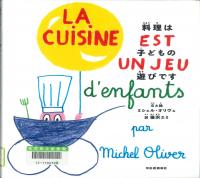
書名 : 料理は子どもの遊びです
著者 : ミシェル・オリヴェ/文と絵、猫沢 エミ/訳
出版社 : 河出書房新社
色鉛筆で描いたようなカラフルな絵が散りばめられたこの本は、フランスで60年以上読み継がれている料理本です。
フランス料理は難しいというイメージを持つ人もいるかもしれません。しかし、この本を読めばタイトルのとおり、「子どもの遊び」のように、簡単で楽しくおいしいフランス料理を作ることができます。
レシピだけでなくフランスと日本の食材や道具のちがいなどの豆知識が書いてあるところも見どころです。本格的なフランス料理のルセット(作り方)がたくさんの絵でやさしく説明されているので、料理をしない人でもまるで絵本のように楽しむことができます。
ページをめくるたびに色とりどりの食べ物を見ていると、あなたもきっと料理をしたくなってきますよ。
児童書のおすすめ(8月19日)

書名 : 恐竜がくれた夏休み
著者 : はやみね かおる/作 武本 糸会/絵
出版社 : 講談社
もし、タイムスリップしてきた恐竜とひと夏を過ごすとしたら、みなさんはどんな日々を送りますか?
主人公の美亜は、夏休みに同じ夢を連続で見るようになります。それは、夜の学校のプールで恐竜が泳ぐ夢。なぜそんな夢を見るのか、その理由を探るため、友人3人と夜の学校に現れるという恐竜のうわさについて調べます。
そのうわさの正体は、なんと現代にタイムスリップしてきた本物の恐竜、ロロだったのです。はじめは戸惑う美亜たちでしたが、元の時代に帰りたがるロロのために、手がかりをともに探すことになります。その中で、地球の未来について知り、美亜たちはとある作戦を立てます。
ロロと関わる中で生じる、美亜たちの関係性の変化や成長も物語の見所です。
なぜロロは現代にやって来たのか、美亜たちが立てた作戦とは、現代にタイムスリップしてきたロロと、小学生グループのひと夏の物語です。
児童書のおすすめ(8月5日)
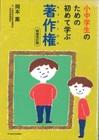
書名 : 小中学生のための初めて学ぶ著作権
著者 : 岡本 薫/〔著〕
出版社 : 朝日学生新聞社
著作権とは何でしょう。
よく耳にしますが、実際には、理解していると自信を持って断言できる人は少ないのではないでしょうか。
著作権とは、「自分で作ったものを勝手に使われない権利」と言うことができます。
この本では、著作権の対象となるものや、誰が著作権を持つのかなど、著作権について身近な例も交えてわかりやすく説明されています。また、著作物の作成・利用時に気をつけるべきことや、著作物を無断で使われないための予防方法なども解説されています。
現代では、インターネットや電子機器が広まり、誰でも物を「作る人」と「使う人」になることができます。そのため、著作権に関する理解を深めることが重要です。ぜひ、自分自身が「著作権を持つとしたら、他者の著作物を利用するとしたら」という見方で読んでみてください。
児童書のおすすめ(7月29日)

書名 : 6days遭難者たち
著者 : 安田 夏菜/著
出版社 : 講談社
「冒険とは、死を覚悟して、そして生きて帰ることである」。
元登山部の美玖、近所に住む亜里沙、そのクラスメイトの由真。薄いつながりの同級生3人は一緒に低山登山にでかけることに。ロープウェイを利用したお手軽日帰り登山のはずでしたが、山頂到着後ほんの少しの油断から誤った道に入り込み、山をさまようことになります。3人が登山に挑戦した理由は様々。その背景をからめながら美玖、亜里沙、由真それぞれの視点でその時の状況が描写されます。
判断ミスが命の危険に直結する登山。ひとつひとつは小さなことなのに、山での遭難はこうして起こるのかとぐっと引き込まれ思わず一気読みしてしまう作品です。冒頭の一文は冒険家植村直己氏が残した言葉で中表紙をめくった1ページ目に書かれています。この言葉の重みを感じ、そしてこの言葉が物語にどんな関わり方をするのかに注目しながら、ぜひ読み進めてください。
巻末の「遭難防止五か条」も必読です。
児童書のおすすめ(7月22日)
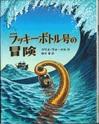
書名 : ラッキーボトル号の冒険
著者 : クリス・ウォーメル/作、柳井 薫/訳
出版社 : 徳間書店
両親に叱られて家を飛び出したジャックが家出先に選んだのは船。ところが運悪く嵐が船を襲い、ジャックは絶海の孤島に打ち上げられてしまいます。
無人島に見えたその島には、長い間ひとりぼっちで本を読んで過ごしていた男ロビンソンと、巨大なカメが住んでいました。
家へ帰りたいと願うジャックに、ロビンソンは手紙を書くことを提案します。ジャックは文字を習っては、手紙をビンに入れて海に流し、助けを待ちわびます。
そんなある日、島に埋められた骸骨の手に握られていた謎の紙きれが、海賊の宝のありかを示していることに気がつきます。
嵐に始まるジャックの海の大冒険。果たしてジャックは宝を探し出し、無事に家へ帰りつくことができるでしょうか。海賊、魔女、しゃれこうべ、宝の地図に謎の呪文まで。奇想天外な物語の展開に、ページをめくる手が止まらない一冊です。
児童書のおすすめ(7月15日)
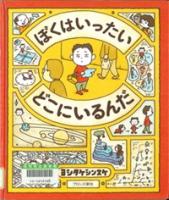
書名 : ぼくはいったいどこにいるんだ
著者 : ヨシタケ シンスケ/作
出版社 : ブロンズ新社
おつかいを頼まれた「ぼく」は、おかあさんが描いた地図がさっぱりわからなくて迷ってしまいました。しかし、みーちゃんのママは目的地をわかるようにと地図にいろいろと描き足してくれて、無事におつかいをすることができました。「ちずがあれば、いまじぶんがどこにいるのかがわかる」「なにかを絵にしてわかりやすくしたものがちずだとしたら…」「じぶんのためだけのちずを、じぶんでつくってもいいよね」と「ぼく」は言います。
自分の部屋の地図やクラスの中での人間関係の地図、今の自分の気持ちの地図。また、未来の地図など発想を膨らませてみると、いろいろな面白い地図を作って観察し、楽しむことができます。物事の仕組みや関係性と問題点、あるいは自分の好奇心など、目に見えない事がらを見えるように(可視化)することで、今や未来が見えてくるし、理解や解決しやすくなったりもします。もうすぐ夏休み、みなさんもオリジナル地図を作ってみませんか。
児童書のおすすめ(7月8日)

書名 : 草のふえをならしたら
著者 : 林原 玉枝/作 竹上 妙/画
出版社 : 福音館書店
物語に登場するのは一風変わった植物の笛です。はじめに出てくるのはねぎの笛。まこちゃんがねぎの青いところをちぎって、ストロー状にして息を吹き込むと、“ブイッブイブイッブブブウ”と音が鳴りました。その不思議な音色に誘われてやってきたのはうすいピンク色のぶた。ぶたはまこちゃんの料理のお手伝いをしたいというのですが…。
その他にもさくらの花びらやささの葉・どんぐりなど、ユニークな笛が登場します。笛が奏でる音色が結ぶ、こどもたちと動物たちとの楽しい交流を描いたおはなしです。
物語の中にはたくさんの植物が出てきます。笛の吹き方も書かれているので、本を読みながら実際に音を鳴らして楽しむこともできます。みなさんの周りにもたくさんの植物がありますね。その植物を笛にして音を鳴らしてみましょう。何か不思議な出来事が起こるかもしれませんよ。
児童書のおすすめ(7月1日)
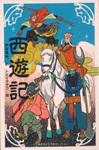
書名 : 西遊記
著者 : [呉 承恩/作] 武田 雅哉/訳 トミイ マサコ/絵
出版社 : 小学館
世界中でさまざまな作品にリメークされている『西遊記』。三蔵法師とともに孫悟空・猪八戒・沙悟浄が仏教の経典を求めて天竺へ向かい、そして帰ってくるという“行きて帰りし物語”です。
『西遊記』は、中国の宋(10~13世紀)の時代に、もとになった旅行記『大唐西域記(だいとうさいいきき)』を「講談」「お芝居」などの形に発展させ、親しまれていました。
観客の前で語るわけですから、とにかく盛り上がり重視!どんどん話を大げさに、面白おかしく脚色していきます。『西遊記』に登場するのが自分勝手でハチャメチャな人ばかりなのも、面白さを追求した結果なのかもしれませんね。
『西遊記』の中で私が好きなのは、不思議な霊力を持つ「人参果」を盗み食いしたお話。師匠の三蔵にバレそうになって、悟空は八戒と仲間割れ、挙句の果てには人参果の木を根こそぎ倒してしまいます。さてこの先、いかなることにあいなりますやら…。続きはぜひ、本を読んでお楽しみください。
児童書のおすすめ(6月24日)

書名 : 働く現場をみてみよう!わたしたちが寝ている時間の仕事
著者 : パーソルキャリア株式会社“はたらく”を考えるワークショップ推進チーム/監修
出版社 : 保育社
世の中には、私たちが寝ている時間帯にお仕事をしている人がいます。実際にその現場を見ることができる機会はなかなかないのではないでしょうか。
急に具合が悪くなったときに診てくださる医師や看護師のように、24時間体制で働く人たちがいます。私たちがお昼の間に楽しく利用するテーマパークは、点検や修理を行う整備士、安全で清潔な環境を保つ清掃員など、たくさんの方の支えがあって成り立っています。表には見えづらい支えがあるからこそ、日頃から安心してスムーズにサービスを利用できるのです。
仕事をしていると、やりがいやうれしいことだけでなく、大変だと感じることもあります。
インタビューのページでは、その仕事の魅力や向いている人など、本音をのぞくことができます。
はっきりとした夢を持っている人も、まだ将来のことはイメージできていない人も、まずは、私たちの前に広がるたくさんの選択肢について知ってみませんか?
児童書のおすすめ(6月17日)

書名 : AIにはない「思考力」の身につけ方
著者 : 今井 むつみ/著
出版社 : 筑摩書房
「いちごのしょうゆをちょうだい」3歳くらいの子どもが言いました。これはどんな意味でしょうか?
この子は「しょうゆ」の存在を知っています。「しょうゆ」は「たべものにかけておいしくするもの」という認識です。「いちごをおいしくするものが欲しい」けれど、その名前を知らない。だから考え、「しょうゆ」という言葉を使って、いちごにかける「コンデンスミルク」を自分なりに表現したのです。このことこそが「ことばの力」と「思考力」で、問題を解決することだと著者は語っています。
私たちは変化の激しい時代に生きています。今ある職業が数十年先にはなくなっている可能性もあるのです。そんな時代を生き抜くために何を身につければいいのか、AIにはなく人間だけにあるものは何なのか、ことばの学びはなぜ大切なのか。認知科学、認知心理学を研究している著者が、自身の著書『親子で育てることば力と思考力』を10代向けに書き直し、やさしく解説しています。
児童書のおすすめ(6月10日)

書名 :まいどばかばかしいお笑いを!
著者 : 赤羽 じゅんこ/作 フジタ ヒロミ/絵
出版社 : 講談社
小学生の天音は、おしゃべりが好きで、家でも学校でもよくしゃべる女の子。
おしゃべりが好きなら落語でも習ってみたら?と、お母さんの知り合いの女性落語家悠々亭若葉さんを紹介してもらいます。
天音は近所の老人ホームで、2か月後に落語の『転失気(てんしき)』を披露することになり、若葉さんに稽古をつけてもらいながら、覚えたことをただ一方的にしゃべるのではなく、相手に伝わるようにしゃべらなければならないことを学び、本番当日を迎えます。
天音の落語は、果たして成功するのでしょうか?最後の「落ち」にも注目です!
巻末には、落語のはじまりや、江戸落語と上方落語の違い、落語の登場人物のくらしなど、ひとくちメモもついています。 物語を楽しみながら、日本文化を学ぶことができる本です。
児童書のおすすめ(6月3日)

書名 : 日本のことばずかん そら
著者 : 神永 曉/監修
出版社 : 講談社
ふと空を見上げてみると空にはたくさんの表情があり、天気や季節、時間帯によって、全く違う顔を見せてくれます。
人々はその空の様子に美しい名前をつけてきました。例えば、晴れを表す言葉だけでも、つゆ晴れや夕晴れ、日本晴れなど様々な呼び名があります。この本では、そのような天気や自然を表す言葉を写真と一緒に紹介しています。
今は雨の季節。たくさんの雨の表情に出合えます。雨の名前を表す言葉はなんと400以上あると言われています。
また、雨かんむりの漢字も350以上あります。その中でも一番画数の多い字は䨻です。 雷が四つ並んだ不思議な漢字は、何と読むのか、どういう意味なのか、本の中で探してくださいね。
この時期、うんざりすることもありますが、雨がどんな風に降っているのか、どんな音がするのか、じっと観察してそれに近い雨の名前を探したり、オリジナルの名前をつけて楽しむのもいいかもしれません。
児童書のおすすめ(5月27日)
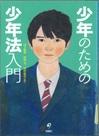
書名 : 少年のための少年法入門
著者 : 山下 敏雅、牧田 史、西野 優花 /監修
出版社 : 旬報社
テレビやネットでは、毎日犯罪のニュースが報道されています。その中では、子どもが起こした犯罪もあります。
罪をおかした子どもがどんな裁判を受け、どんな扱いを受けるのかについては、「少年法」という法律で決められていますが、名前は聞いたことがあっても、詳しい中身は知らないと思います。
この本の監修者の1人、山下弁護士は、子どもたちのための法律が、子どもたちに知らされていないのは問題だと考え、この本を作られました。
「少年犯罪は年々増加し、凶悪化している」という話を聞いたことがあるかもしれません。しかし、実は少年犯罪は2003年以降減少し続けており、凶悪事件(殺人)についても96件(2003年)から52件(2019年)と大きく減少しています。
「犯罪は自分と違う世界で起きている」「法律は自分と関係なさそう」という考えから、「少年犯罪は年々増加し、凶悪化している」というイメージが持たれ、そこから少年法が厳罰化の方向に改正されてきているそうです。
この本を読み終えたとき、少年法についての正しい知識が得られ、皆さんが新しい社会を作る一歩になると思います。
児童書のおすすめ(5月20日)

書名 : ほんとうのリーダーのみつけかた
著者 :梨木香歩/著
出版社 :岩波書店
みなさんが思うリーダーのイメージはどんな人ですか。強そうで堂々としていて、自信満々な人。そういうどことなく強そうな雰囲気の人がリーダーのイメージだと感じる人もいるかと思います。でも、みなさんの中にもそのような雰囲気の人の意見に、流されてしまったことがある人もいるのではないでしょうか。
あなたのほんとうのリーダーは、両親、友達、先生よりもあなたのことを全て知っている。しかも、あなたの味方でいつだってあなたの立場に立って考えてくれる人がリーダーではないでしょうか。
この本の著者・梨木香歩さんが言っています。「いつか、私などの想像もつかない、伸びやかな精神を持つ次世代が現れんことを夢見つつ祈りつつ」と。
あなたの周りにリーダーとなれる人はいませんか。この本の中にリーダーとなれる人物像が書かれています。
児童書のおすすめ(5月13日)

書名 : 作ろう!フライドチキンの骨格標本
著者 : 志賀 健司/著 江田 真毅、小林 快次/監修
出版社 : 緑書房
最近の研究では「すべての鳥は恐竜の子孫」といわれています。みなさんはすでにご存じかもしれませんね。
この本では「”現生恐竜”の代表」とされるニワトリの骨を使って、なぜ鳥が恐竜の子孫だといえるのか、その理由を探ります。
骨の歴史を学び、恐竜とニワトリの類似点を見つけた後は、フライドチキンを「採集」し、骨格標本作りの始まりです。チキンを食べたら満足してしまいそうですが、ここからが本番。薬品処理をしたり、組み立てたり、根気のいる作業が続きます。
骨格標本作りは大変ですが、過去ではどんな姿だったのか、未来ではどう姿を変えていくのか、想像すると、なんだかワクワクしませんか。本を通して、連綿と続く生命の歴史を感じることができますよ。
児童書のおすすめ(5月6日)

書名 : 虫ぎらいはなおるかな?昆虫の達人に教えを乞う
著者 : 金井 真紀/文と絵
出版社 : 理論社
あなたは虫が好きですか?嫌いですか?
虫が好き・嫌いとなる分岐点、ゴキブリが「汚いもの扱い」されているのは実は不当であること、なぜ動物の病院はあるのに虫には病院がないのか、アメンボはあめ玉の匂いがするからアメンボ、日本ほど「虫とり」がポピュラーな国は珍しい…。この本では、昆虫の達人7名の教えによる虫についての実態や意外と思える一面が、ユーモラスにわかりやすく散りばめられています。
達人は「虫が嫌いなのは観察が足りないから」と言い、虫が嫌いな作者の思いも達人と出会うなかで、「知ってから好き嫌いを判断すればいいのに、知らないで嫌いになるのは不当だ」と変化していきます。カニが怖くて嫌いな私は、一つ穴の中でカニとカエルが重なりあい冬眠するほほ笑ましい姿を見つけ、嫌いレベルが少しダウン。知らず嫌いは日々のなかに多々あるけど、「嫌い」なことと上手に付き合うことができるようになれたらいいですね。
児童書のおすすめ(4月29日)

書名 : すこしずつの親友
著者 : 森埜 こみち/著
出版社 : 講談社
一人でいるとさみしい、親友がほしい。そう感じることはありませんか。 この本に登場するのは、今すぐ親友がほしい「わたし」と、すこしずつの親友がいる「伯母さん」です。
この「すこしずつの親友」とは、長い時間を共にして、心を許して話ができる親しい友人のことではありません。
例えばこんな話が紹介されています。海外の空港で、伯母さんは男性にスーツケースをぶつけてしまいました。謝る伯母さんに、彼は眼だけでうなずくように笑います。お互いの気持ちが通じ合った一瞬の出来事でした。伯母さんは彼のことを「すこしずつの親友」だと言います。
短時間の出会いでも、心の交流をしたり、忘れられない思い出になったり、新たな学びを得たりすることができます。あなたが孤独を感じる時、あなた自身の「すこしずつの親友」を思い出してみませんか。
児童書おすすめ(4月22日)
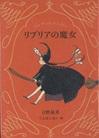
書名 : リブリアの魔女
著者 : 日野 祐希/著
出版社 :アリス館
この本は魔法が使える世界で魔導師を目指している、メノアという女の子の物語です。
メノアは、弟子入り試験をかねていた魔法学院の卒業式を風邪で欠席してしまいました。このままどこにも弟子入りできなければ、魔導師になることができません。いとこのつてを頼りに、伝説の天才魔導師のシェリルの元へ弟子入りを頼みに行きます。 向かった魔導書工房には、美しいけれど、どこかおとぼけたオーラを漂わせている、不思議な魔導師がいました。
しっかりもののメノアと、おとぼけシェリルのでこぼこコンビは、無事に師弟になれるのでしょうか?
メノアは弟子入りの試験のために国の各地を巡り、魔導書の材料を集めてくることになります。旅先では知らないことや初めてのことばかり。不安でいっぱいになりながらも様々な試練を乗り越えていきます。
失敗を恐れずに挑戦することの大切さを教えてくれる物語です。
